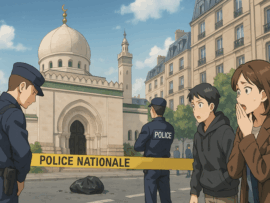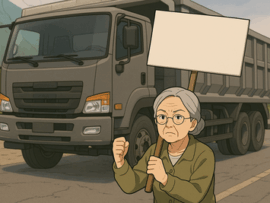ジョージ・スティーヴンス監督は、『陽の当たる場所』や『ジャイアンツ』といった名作でアカデミー賞監督賞を受賞した巨匠でありながら、第二次世界大戦に従軍し、その目で戦争の現実を映像に収めました。ダッハウ強制収容所の解放、パリ解放後にドイツ協力者の髪を丸刈りにする市民の群衆など、「映像の世紀」を象徴する数々の衝撃的なシーンが、彼のレンズを通して記録されています。NHKの『高精細スペシャル ヨーロッパ2077日の地獄』シリーズは、この時代の35ミリフィルムを高精細かつカラー化する画期的な試みを行い、当時の色彩と雰囲気を現代に蘇らせました。
 第二次世界大戦中の様子を捉えた35ミリフィルムが、NHKの高精細・カラー化技術によって蘇る様子。歴史的映像の保存と伝承の重要性を示す。
第二次世界大戦中の様子を捉えた35ミリフィルムが、NHKの高精細・カラー化技術によって蘇る様子。歴史的映像の保存と伝承の重要性を示す。
戦争を映し出す視点:ジョージ・スティーヴンス監督の記録
各国のプロパガンダ映画とは異なり、スティーヴンス監督は「監督生命を投げ打つ」覚悟で西部戦線に臨み、客観的な視点で映像を撮影したとされます。しかし、彼自身の至言である「すべての映像はプロパガンダだ」という言葉が示すように、映像は常に特定の意図や視点を含んでいます。戦勝国が敗者を映し出す映像や、ナチスに抵抗したフランス国民が、敗戦後に協力者に対して躊躇なく暴力を振るう姿など、映像は多面的な現実の一側面を切り取ります。第二次世界大戦が「映像の世紀」と呼ばれたにもかかわらず、その全貌は映像のみでは決して解明できない複雑なものです。映像の背後にある文脈や、撮影者の意図、編集の力が、視聴者の認識に大きな影響を与えることを私たちは常に意識しなければなりません。
ジャーナリズムの教科書「八月の砲声」が示すもの
戦争とジャーナリズムの関係を深く考える上で、第一次世界大戦のノンフィクションであるバーバラ・W・タックマン著『八月の砲声』(山室まりや訳・ちくま学芸文庫)は、その教科書的存在です。1963年にピューリッツァー賞を受賞し、多くのノンフィクション作家に読み継がれています。1914年6月のオーストリア皇太子夫妻サラエボ暗殺事件を第一次世界大戦の発端としながらも、この書籍の真骨頂は、「なぜ」戦争が起きたのかではなく、「どのように」戦争が進行していったのかを描き出している点にあります。
同盟国側(ドイツ、オーストリア=ハンガリー二重帝国、オスマン帝国など)と連合国側(イギリス、フランス、ロシア、日本、アメリカなど)の各国の指導者たちが、同盟や協商を通じて目指していた思惑が、いかにして判断ミスや偶発的な出来事によって狂い始め、やがて大戦へと発展していったのかを詳細に記述しています。兵士だけでも約1000万人もの死者と2000万人以上の負傷者を出したこの戦争の経緯は、単一の原因で説明できるものではありません。ジャーナリズムの焦点は、指導者たちの行動、そして戦争によって甚大な被害を被った国民たちの視点に置かれ、「なぜ」ではなく「どのように」が重要視されるのです。
複雑な現実を読み解く:ネットワーク・サイエンスの示唆
サラエボ事件という「なぜ」戦争が起きたかへの答えは、本質的には不十分です。最新の科学理論である「ネットワーク・サイエンス」は、この歴史的アプローチに新たな光を当てます。様々な事象が複雑なネットワークを形成し、相互に作用し合うことでコアとなる結節点を作り出し、最終的に大きな結果を生み出すという理論です。例えば、地震がなぜ起きるのかを予測するのが困難であるように、戦争のような大規模な歴史的出来事もまた、単一の原因ではなく、無数の要素が絡み合った複雑なネットワークの結果として生じます。『八月の砲声』の視点は、まさにこうした複雑系の理解を先取りしていたとも言えます。ジャーナリズムが「どのように」に焦点を当てることは、表層的な原因究明に留まらず、歴史の深層にある複雑な構造を読み解く上で不可欠な視点を提供します。
歴史を動かす無数の要素がどのように絡み合い、連鎖していったのかを理解することは、過去の教訓を現在に活かし、未来を考える上で極めて重要です。「映像の世紀」の記録から「八月の砲声」の分析まで、多角的な視点から戦争と社会のつながりを深く考察し、複雑な世界情勢を理解する手助けとなるでしょう。