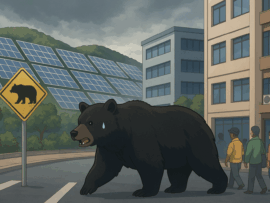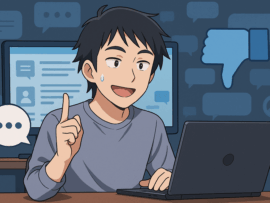日本の高齢化が進む中、訪問介護サービスの需要は高まる一方、現場では深刻な人手不足が課題となっています。特に注目されるのが、サービスを支えるホームヘルパーの高齢化です。70代や80代のベテランヘルパーが現場の最前線で奮闘する一方で、なぜこの重要な仕事に若い人材が集まらないのでしょうか。本記事では、訪問介護の現状と、その背景にある構造的な問題に迫ります。
高まる需要と深刻化する人手不足の実態
東京都西東京市にある訪問介護事業所「訪問介護 ひばり」では、常勤・非常勤合わせて35人のホームヘルパーが働いています。社長の大澤幸一郎氏(48)は、「人は足りていません。オーバーワークにならないよう配慮する結果、ご依頼をお断りせざるを得ない状況も生まれています」と、現場の厳しい状況を語ります。同事業所のヘルパーの年齢層は、全体の約6割が60代と70代で占められ、中には81歳のヘルパーも活躍しています。高齢のヘルパーが不可欠な戦力となっている現状が浮き彫りになります。
高齢ヘルパーの「強み」と直面する課題
ひばりで働く三島和子さん(73)は、70代、70代後半、90歳の女性3名宅を担当し、週に1回ずつ自転車で訪問しています。月収は「月に2万円ちょっと」と語る三島さんの仕事は多岐にわたります。例えば、脳梗塞で右半身が不自由な70代の利用者には、リハビリパンツの交換を手伝ったり、デイサービスへ行くためのリュックサックの中身を一緒に点検したり、洗濯をしたりと、「利用者さんの自立支援を促す側面が強いので、『一緒にやる』がとても大事なんです」と、その業務の特性を説明します。
社長の大澤氏は、三島さんのような高齢のホームヘルパーが持つ「強み」を強調します。「長い経験と、利用者の方と同じ目線の高さであることによる気づきもある。若いヘルパーさんより安心してサービスに入っていただける面は確かにあると思います」。長年の経験に裏打ちされた深い理解と共感は、利用者にとって大きな安心材料となっています。
 82歳のベテランホームヘルパーが、訪問介護サービス中に利用者と笑顔で会話を交わしている
82歳のベテランホームヘルパーが、訪問介護サービス中に利用者と笑顔で会話を交わしている
しかしながら、高齢化に伴うマイナス面も無視できません。大澤氏は、「以前は一日に6件、7件と訪問をこなせていた方も、高齢による体力的な問題で訪問件数が減ってきてしまう。そこはやはり大きいです」と、体力的な制約がサービス提供能力に影響を与える現実を指摘します。
なぜ若者は訪問介護の仕事に集まらないのか:専門性の壁
では、なぜ訪問介護の現場に、特に若い世代の人材が集まらないのでしょうか。東洋大学教授で高齢者福祉・介護を専門とする高野龍昭氏は、その「最大のポイント」として、ホームヘルパーに求められる「専門性の高さ」を挙げます。
高野氏によれば、訪問介護の業務は、ヘルパーが一人で利用者の自宅を訪問し、介護業務を行うという特殊性があります。利用者の中には認知症を患っている方も多く、予期せぬイレギュラーな事態が発生することもしばしばです。会社の中での業務であれば、先輩にすぐにアドバイスを求められますが、訪問介護の現場では、新人であってもすべて自分一人で判断し、対応しなければなりません。「非常に高い専門性が求められ、介護の仕事を志す人の中でも特に訪問介護はハードルが高いんです」と高野氏は説明します。この、一人で判断し行動する高い専門性と責任感が、若い人材がこの職種に踏み出す上での大きな障壁となっているのです。
まとめ:訪問介護の未来への提言
訪問介護は、利用者の生活を支える上で不可欠なサービスであり、その需要は今後も増加が見込まれます。しかし、高齢化する現役ヘルパーの身体的負担と、若年層の参入を阻む「高い専門性」の壁という二重の課題に直面しています。この現状を打開し、持続可能な訪問介護サービスを提供していくためには、単に労働条件を改善するだけでなく、新人ヘルパーが自信を持って一人で現場に立てるような、より実践的で手厚い研修制度の充実、あるいは遠隔でのサポート体制の強化など、訪問介護特有の「専門性の高さ」に対する具体的な対策が求められます。多様な働き方を許容し、若い世代が魅力を感じ、安心して長く働ける環境を整備することが、日本の介護業界全体の未来を左右する鍵となるでしょう。
参考文献
- AERA 2025年8月25日号(Yahoo!ニュース配信記事)「82歳のヘルパーも現役、訪問介護が深刻な人手不足なワケ」を基に作成
- 【気になるデータ】訪問介護事業の「倒産」件数の推移(グラフ)