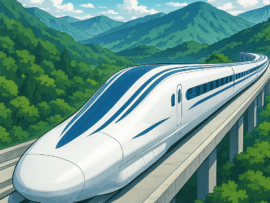あちらにもこちらにも、高層タワーマンション(タワマン)が林立し、日本の都市景観は大きく変化しました。2024年末時点で全国に1561棟ものタワマンが存在すると言われるほど、その勢いは止まりません。タワマンは地域の生活、景観、そして価値を一変させる一方で、その足元には長きにわたり地元の人々が築き上げてきた生活圏が今も広がっています。本記事では、垂直に伸びるタワマンの陰で、水平に広がる歴史ある街並みを守り続ける「タワマンだけじゃない街」の姿に注目し、レポートします。特に今年は昭和100年という節目の年。曳舟・京島界隈では、100年前のデベロッパーの想いと現代のデベロッパーのビジョンが交差する、独自の都市物語が息づいています。
 墨田区曳舟駅周辺に立ち並ぶ現代的なタワーマンション群
墨田区曳舟駅周辺に立ち並ぶ現代的なタワーマンション群
曳舟の名の由来と現代の変貌
東京都墨田区に位置する曳舟エリアには、東武線の曳舟駅(墨田区東向島2-26-6)と京成曳舟駅(墨田区京島1-37-11)があります。これら二つの駅を分けるように走る曳舟川通りは、その名の通り、かつて江戸時代に整備された曳舟川という水路が流れていました。人々や馬が舟を引いて利用していたことから「曳舟」という地名が生まれたと言われています。
現在、東武線曳舟駅と京成曳舟駅の周辺は再開発が著しく進み、数棟のタワマンが建設されました。曳舟駅前から南の方角を望むと、東京スカイツリーの壮麗な姿がよく見え、現代的な都市の風景が広がっています。
京島の長屋が語る100年前の開発史
ところが、京成曳舟駅から南東に広がる京島地区へと足を踏み入れると、その風景は一変します。そこには100年前に建てられたとされる長屋が今も数多く残り、まるで時が止まったかのような趣を醸し出しています。この地域は、大正時代後期から昭和時代初期にかけて、越後からやってきた大工集団によって大規模な住宅開発が行われた歴史を持ちます。
それまでの京島は、広大な田畑が広がる湿地帯でした。しかし、この地に驚くべき速さで住宅が開発され、新たな生活空間が生まれました。100年前の大規模な開発と、タワマンを含む現代の再開発。時代は異なりますが、二つの開発の波が京島・曳舟の地で交差しているのです。
関東大震災と「越後三人男」の功績
曳舟駅周辺のタワマン群を望む京島界隈には、既述の通り昭和初期までに建設された長屋群が残っています。この一帯は東京都内でも有数の「木造住宅密集地域」として知られ、万が一火災が発生すれば延焼の危険性が高いことから、東京都も長年にわたり改善事業を展開しています。
1923年(大正12年)に発生した関東大震災は、東京府民(当時)に甚大な被害をもたらしました。死者・行方不明者は約10万5000人、全壊・焼失・流失した家屋は21万2000棟以上にも上り、家屋を失った人々のため、早急に大量の住宅が必要とされました。幸いなことに、京島地区は震災の被害が比較的少なかったため、この地に多くの長屋が建設されることになります。この長屋建設の主要な担い手となったのが、「越後三人男」と呼ばれる大工集団でした。彼らの功績は、都市の復興と新たな街づくりに大きく貢献したと言えるでしょう。
曳舟と京島は、タワマンの象徴する未来的な都市開発と、長屋に息づく歴史の積み重ねが共存する、極めて魅力的なエリアです。この街を深く探ることは、単なる再開発の歴史を知るだけでなく、日本の都市が歩んできた道のり、そして未来への示唆に富んだ知見を与えてくれます。私たち「日本ニュース24時間」は、このような多層的な都市の物語を今後も追い続けていきます。