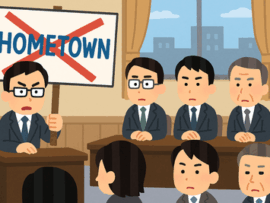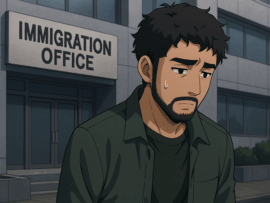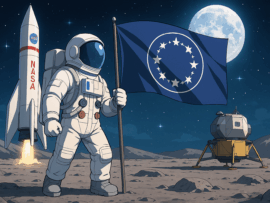中国で、旧日本軍の侵略を描いた映画『南京写真館』(南京照相馆)が異例のヒットを記録し、大きな議論を呼んでいます。7月25日の公開以来、興行収入は8月22日時点で26.5億元(約548億円)を超え、観客の涙を誘う作品として注目されています。南京事件を題材としたこの作品は、歴史の記憶を呼び起こすものとして評価される一方で、悲惨なシーンで号泣する子どもたちが多数見られたという報告もあります。特に、河南省で9歳の子どもが鑑賞後に大切にしていた日本のアニメのカードをすべて破り捨てたという報道は、中国現地で物議を醸しました。果たして、この現象は「記憶の継承」の成功と呼べるのか、それとも「恨みの再生産」に繋がりかねないのか、複雑な問いを投げかけています。本作の観客の4割以上が25歳未満という若年層であることから、次世代への戦争記憶の継承がどのような形で行われるべきか、日本社会においても関心が高まっています。
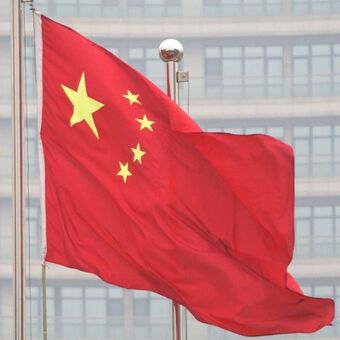 旧日本軍の侵略を描く中国映画『南京写真館』のポスター。劇中のワンシーンで、歴史の記憶を呼び覚ます作品として注目を集めている。
旧日本軍の侵略を描く中国映画『南京写真館』のポスター。劇中のワンシーンで、歴史の記憶を呼び覚ます作品として注目を集めている。
中国ネットで活発化する「子どもへの抗日映画見せるべきか」議論
先日、中国の映画学専門の大学教授の友人から、『南京写真館』を子どもに見せるべきかどうかをめぐるショート動画が共有されました。その動画には一般のネットユーザーが出演し、感情に流されず理性的に作品を分析していた点が印象的でした。かつては抗日映画の表現に関する話題はセンシティブなものとして扱われがちでしたが、近年はネットの発達によって、ある程度自由に議論できる雰囲気が醸成されつつあります。このショート動画には、「子どもに歴史教育をすべきだ」という意見が寄せられる一方で、「この映画を子どもに見せたくない」という親の声も少なくありませんでした。例えば、あるコメントでは「私は自分では見に行かないし、子どもを連れて行くなんてもってのほか。昔、似たような映画を見てすごく怖かった記憶があって、悪夢まで見たことがある」と、過去の経験からくる抵抗感が表明されていました。
「80年前の軍国主義と今の日本人は別」―冷静なネットユーザーの声
多様な意見が交わされる中、非常に冷静な視点を示すネットユーザーのコメントも目を引きました。そのコメントには「思い出すのは、2020年2月、新型コロナが中国で拡大したとき、日本から届けられた支援物資に添えられた言葉だ。武漢には『山川異域、風月同天』(山や川は違う土地にあるけれど、風も月も同じ空の下にある)、湖北には『豈曰無衣、与子同裳』(衣なきと言うなかれ、君と共に裳を着よう)、大連には『青山一道同云雨、明月何曾是两郷』(遠く離れていても、同じ山に同じ雨が降る。月は一つ、君と私の心を隔てるものはない)。80年前の日本の軍国主義と、今の日本の人々とは、まったく別の存在だ」と記されていました。この意見は、歴史的事実と現代の日中関係、そして人々の間に存在する友好的な感情とを区別しようとするものです。映画が喚起する感情と、現実世界での交流との間に生じる認識の複雑さを浮き彫りにしています。

『南京写真館』の異例のヒットとその反響は、中国における戦争記憶の継承、特に若年層への歴史教育のあり方、そしてそれが日中関係に与える影響について、多角的な視点から議論されるべきであることを示唆しています。過去の悲劇を風化させずに記憶を次世代に伝えることの重要性は疑いようがありませんが、その方法が「憎悪の再生産」に繋がることがないよう、冷静かつ理性的な対話が不可欠です。映画が提起する感情的な側面と、日中両国の人々が築いてきた現代の友好関係とのバランスをいかに取るか、今後の動向が注目されます。