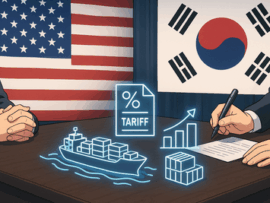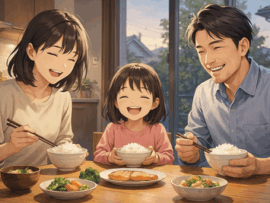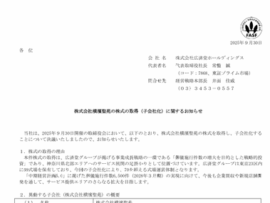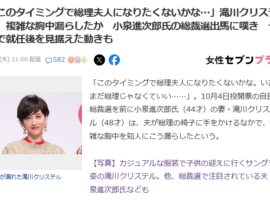三田紀房氏の人気受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が、教育と受験の「今」を深く掘り下げる連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。今回の第79回では、急速に進化する生成AIと教育現場での向き合い方について考察します。技術革新が勉強や学習意欲にどのような影響を与えるのか、そして高等教育機関の意義が問われる現代において、私たちはどのように「学び」と向き合うべきか、その本質に迫ります。
東大生が明かす「AIチート」レポートの実態と見破られる理由
『ドラゴン桜2』では、東大合格請負人・桜木建二が生徒に対し、常に最新のアプリを活用し、自らをアップデートし続けることが東大合格への秘訣だと説きます。この言葉は、現代のAI勉強法にも通じる教訓を含んでいます。今年8月に発表されたOpenAIのChatGPT新モデル「GPT-5」は、「博士号を持つ友人」レベルと評されるほどその性能を向上させており、私たちの学習環境に大きな変革をもたらしています。
しかし、その一方で、大学の成績評価シーズンには、AIを不適切に利用した学生のレポートに頭を悩ませる教員の声がSNSで散見されます。「存在しない論文が参考文献として挙げられている」「AIの出力をそのままコピーしたと思われる『他に聞きたいことはありますか』という文言が含まれていた」など、生成AIレポートのずさんな実態が明らかになっています。
 三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』の表紙イラスト
三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』の表紙イラスト
残念ながら、東京大学とてこの問題の例外ではありません。筆者の友人の中には、AIの不適切な使用が原因で単位を落とした者もいます。
もちろん、AIの利用そのものが「NG」というわけではありません。筆者自身もAIを活用した勉強の一環として、レポート作成時に論文要約AIで文献の要点を把握したり、自分の主張の論理性を確認したり、校閲AIで文章表現を推敲したり、参考文献の書式統一を行ったりと、AIの得意分野を積極的に活用しています。
同じ授業で、ある時はAIを全く使わず、またある時はAIの助けを借りて小レポートに取り組んだ友人の例では、AIを使用した時の方が良い評価を得られたといいます。彼はもともと東大生の中でもトップレベルの成績の持ち主であり、「より正確に、より厳密に」という意図のもとにAIを使用する姿勢は、これからの教育現場におけるAI利用の理想形と言えるでしょう。
「消化試合」化する大学生活への警鐘:学びの意欲を問う
より深刻な問題は、生成AIが作成した回答の痕跡を消す努力すらしないほど、学習意欲の低下が顕著なケースです。AIが書いたものを丸ごと写してレポートを提出するような心構えは、もしかすると、元々持ち合わせていた「学びへの意欲のなさ」が、AIというツールによって一層露呈した結果かもしれません。
自分で選んだ進路であり、自分で選んだ授業であるはずなのに、その選択に対して主体的に向き合おうとしないのは、一体どういうことなのでしょうか。「これは自分にとって意味がない。だから、本当にやりたいことに時間を使うため、AIに代替させる」という割り切りがあるならば、まだ理解できます。しかし、「私はこれをやりたい。だが、どんなに頑張ってもAIが出すものに及ばない」という無力感を生み出しているのであれば、学びの意味そのものを見つめ直す必要があります。
さらに、高等教育機関として、「学問に興味はないが、大学を卒業しないと就職できないから仕方なく取り組む」という意識が蔓延しているのであれば、その構造自体が修正されるべきだという警鐘でもあります。これまで、たとえ意欲が全くなかったとしても、各種の課題を自力でこなす必要があったため、強制的にでも「学びのフレームワーク」を身につけさせることができました。しかし、それすらもAIが代替するとなれば、学生にとっても教員にとっても、長い「消化試合」のような大学生活が生まれてしまうでしょう。これは、大学が本来持つべき存在意義が根本から問われる事態です。
ツールの選び方は、単なる利便性だけでなく、学びの本質にも関わります。AIの急速な発展に代表されるように多くのツールが登場していますが、商業的な側面ばかりが追求され、かえって学びを阻害しうるツールも少なくありません。例えば、講義を自動的に要約してくれるツールをどの程度使用すべきか、という問題もその一つです。常に技術のアップデートを追い続けると同時に、あえてツールを使わないという選択ができるかどうかも、現代の学習者にとって重要な判断基準となるでしょう。
まとめ
生成AIと教育の融合は、計り知れない可能性を秘める一方で、私たちの「学び」に対する根本的な問いを投げかけています。東大生の土田淳真氏が指摘するように、AIは学習を効率化し、深い理解を助ける強力なツールとなり得ますが、その利用の仕方を誤れば、学習意欲の低下や高等教育機関の意義の喪失にも繋がりかねません。
重要なのは、AIを単なる「チートツール」としてではなく、主体的な学びを深めるためのパートナーとして捉え、賢く活用する姿勢です。東京大学の学生たちが直面している現実から見えてくるのは、技術の進化を追い続けるだけでなく、自分自身の学びの意味を常に問い直し、あえてツールを使わないという選択肢をも含めた、本質的な学習へのコミットメントが不可欠であるということです。未来の教育において、AIは単なる道具ではなく、私たち自身の「学ぶ力」と「学びへの意欲」を試す試金石となるでしょう。