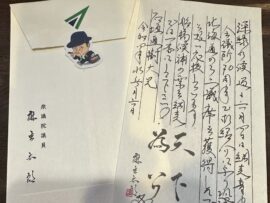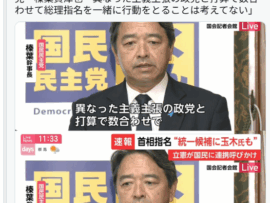45年前の夏夜も、今日の東京を思わせる蒸し暑さだった――。1980年8月19日、日本の首都・新宿駅西口で、発車を待つ京王帝都バスが突如放火され、死者6名、重軽傷者14名を出す大惨事となりました。これは日本の無差別殺人の歴史において、最悪の惨劇の一つとして記憶されています。この事件が社会に大きな波紋を広げたのは、その甚大な被害だけでなく、後に丸山博文(事件当時38歳)服役囚が裁判で「心神耗弱」と判断され、死刑を免れたことにも起因します。半世紀近く経った今なお、「心神喪失」や「心神耗弱」における責任能力の有無、そして刑罰の軽重を巡る議論は繰り返されますが、その原点とも言えるのがこの「新宿バス放火事件」です。本記事では、月刊誌「新潮45」が2007年に掲載したノンフィクション作家・福田ますみ氏による詳細な記事を再録し、この歴史的事件を通じて犯罪と責任能力、そして日本の刑法のありようについて深く考察する機会を提供します。
 放火事件で燃え盛るバスの炎、その高さは20メートルに達したとされるイメージ
放火事件で燃え盛るバスの炎、その高さは20メートルに達したとされるイメージ
突如現れた20メートルの炎と炭化した遺体の発見
事件発生から約40分後、駆けつけた消防隊によって火は消し止められました。しかし、バスの後部座席には、完全に炭化した無残な遺体が3体、座ったままの姿勢で発見されるという、想像を絶する光景が広がっていました。昭和55年8月19日午後9時過ぎ、東京・新宿駅西口の京王百貨店前バス乗場での出来事です。乗客約30人を乗せた中野車庫行きの京王帝都バスは、9時10分の発車時刻を待っていたのでした。突如出現した20メートルもの巨大な火焔は、傍らの京王百貨店の5階にまで達し、新宿の夜空を焦がしました。
1980年新宿バス放火事件で炎上後、黒焦げとなったバスの残骸と惨劇の現場
凄惨な火災現場:生存者が語る恐怖の瞬間
当時の生存者たちは、この信じがたい惨劇を肌で経験しました。後部出口近くの長椅子でまどろんでいた21歳の男子学生は、突然聞こえた男の罵声に目を覚まします。「馬鹿野郎! なめやがって」――その言葉の直後、足元の床に置かれた新聞紙の束が燃え上がっているのを目撃します。水のような液体が新聞紙の上に撒かれた瞬間、耳をつんざくような爆発音と共に炎は瞬く間にバスの天井をなめ尽くしました。彼は咄嗟に顔を手で覆い、燃え盛る炎の中を出口を求めて逃げ惑い、自身の髪の毛が燃えていることすら認識しました。
また、最後部の座席で熱心に本を読んでいた21歳の女性は、突然目の前に巨大な炎の壁が現れたことに何が起こったのか理解できませんでした。炎と煙、そして乗客たちの絶叫が車内に充満し、逃げ道を失います。しかし、割れた窓ガラスが目に入った瞬間、彼女はそこに身をねじ込み、頭から路上に落下して九死に一生を得ました。着ていた化繊の洋服は溶けて肌にはりつき、全身に重度の火傷を負った彼女は「熱い、熱い」と転げ回りましたが、周囲を取り囲んだ何百人もの野次馬は、ただその光景を見ているだけだったという、人間の無関心さをも浮き彫りにする証言を残しています。
法的責任を巡る議論の原点として
「新宿バス放火事件」は、単なる悲劇的な事件としてだけでなく、日本の刑事司法における「責任能力」という概念を深く問い直す、極めて重要な意味を持つ事件となりました。丸山博文服役囚への「心神耗弱」判決は、その後、心神喪失や心神耗弱状態の者が犯した犯罪に対する責任能力の有無、そしてそれに応じた刑罰の軽重について、現在に至るまで続く社会的な議論の原点となったのです。この事件は、社会に犯罪と精神疾患、そして司法のあり方について深く問いかけることとなりました。本記事は、その詳細を伝えるべく「新潮45」(2007年2月号)に掲載されたノンフィクション作家・福田ますみ氏の綿密な調査に基づく内容を再録したものであり、この歴史的事件を再検証する価値は今日でも非常に大きいと言えるでしょう。
この恐るべき事件が突きつけた問いは、現代社会においてもなお、私たちに重くのしかかっています。犯罪の背後にある人間の精神状態をどこまで考慮すべきか、そしてその判断基準は適切か。これらの問いは、日本の法制度、さらには人としての倫理観について、継続的な議論と深い考察を促すものです。
参考文献
- Source link
- 月刊誌「新潮45」2007年2月号 (ノンフィクション作家・福田ますみ氏による記事)