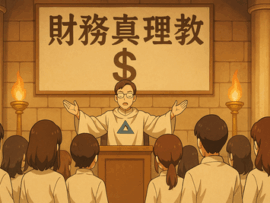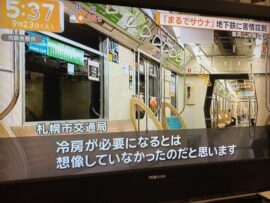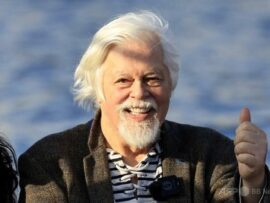警視庁には、各国大使館との円滑な連携を図るための「大使館リエゾン(連絡係)」という特別な職務が存在します。その実態は、外交官が事件や事故に巻き込まれた際、現場の警察官が持つ捜査権と、外交官に与えられた外交特権との間に生じる摩擦、さらには言語の壁という複数の課題を解決する重要な役割を担っています。元警視庁公安部外事課でリエゾンとしての勤務経験を持つ勝丸円覚氏は、双方の論理を理解するリエゾンの存在が不可欠であると指摘しています。本稿では、勝丸氏の著書『日本で唯一犯罪が許される場所』の内容を基に、このユニークな仕事の全貌に迫ります。
東京に息づく「小さな外国」:大使館と警察の接点
東京都港区に集中する各国大使館は、それぞれが警察の捜査権が及ばない外交特権を有し、各国の事情や特色に基づいて活動しています。中にはカウンターインテリジェンス(防諜)を意識した人員を配置している国もあり、これらはまさに東京都内に点在する「小さな外国」と呼べるでしょう。
外務省だけでなく、なぜ警察も大使館との接点を持つ必要があるのか。その理由は、外交特権を悪用した犯罪の存在が挙げられます。外務省は儀典官室を通じて外交官に対し「ペルソナ・ノン・グラータ(好ましからざる人物)」を通告する権限を持つものの、犯罪捜査は行えません。一方、警察は犯罪捜査の権限を持つものの、大使館や公邸内への立ち入りや外交官の身柄拘束は外交特権により制限されます。互いの強みと弱みを補完し、この間の隙間を埋める役割こそが、警視庁の大使館リエゾンに求められているのです。
捜査権と外交特権の衝突:リエゾンが担う橋渡し
外交官が関わる事件では、日本の法律と国際法である外交特権が複雑に絡み合います。このような状況下で、捜査を進める警察官と特権を持つ外交官の間でスムーズなコミュニケーションを確立することは極めて困難です。特に、事件の初期段階での情報収集や、必要に応じた外交当局との調整は、専門的な知識と経験がなければ成り立ちません。リエゾンは、このデリケートな状況において、双方の法的立場と文化的背景を理解し、通訳や説明役として機能することで、摩擦を最小限に抑え、事態の解決へと導きます。
 外交官との交渉にあたる警視庁の担当者のイメージ
外交官との交渉にあたる警視庁の担当者のイメージ
彼らは、外交官が持つ特権を悪用したと疑われる事例であっても、直接的な捜査や逮捕が困難な中で、外交チャネルを通じて問題を提起し、本国への強制送還(ペルソナ・ノン・グラータ)などの対応を促すための重要な役割を担います。これにより、日本の法治国家としての原則を維持しつつ、国際関係への影響を考慮した上で、適切な対応を図ることが可能となるのです。
警視庁外事課リエゾンの多岐にわたる専門業務
大使館リエゾンの業務は、事件対応に留まりません。大使館に対し、防災・防犯に関するブリーフィングを行うのも重要な仕事の一つです。日本の警察ならではの視点から、どのような行為が犯罪となり得るか、また犯罪者がどのような場所を標的とするかといった具体的な情報提供は、外務省ではカバーしきれない専門性を要します。日本の法令説明は外務省でも可能ですが、国内の防災・防犯事例に関する深い知見は警察の専門分野であり、ここでリエゾンがその真価を発揮します。
さらに、外交官が関与する犯罪が国際的なもの、例えばインターポール(国際刑事警察機構)が登場するような規模に発展する可能性もあります。各国大使館に駐在するCIAやFBIのような情報機関、あるいは法執行機関との連携が必要となる場合、その窓口は国の警察庁となりますが、大使館が東京に所在していることから、現場での実務的な対応は警視庁、特に外事課のリエゾンが担当することになります。外交特権を完全に理解しているとは言えない交通部や生活安全部、刑事部の捜査官では、効率的な捜査や連絡が困難であるため、外交分野に精通したリエゾンの存在が不可欠となるのです。
結論
警視庁の大使館リエゾンは、日本の首都に存在する「小さな外国」である大使館と、日本の法執行機関との間で、外交特権、捜査権、言語、文化といった複雑な要素が絡み合う中で、円滑な関係を築き、日本の治安と国際的な協調を保つ上で極めて重要な役割を担っています。彼らの専門的な知識と経験は、外交官が関わる犯罪の解決から、大使館の防災・防犯対策、さらには国際的な情報・法執行機関との連携まで、多岐にわたる場面で不可欠であり、日本の国際社会における信頼性を支える見えない基盤となっていると言えるでしょう。
参考資料
- 勝丸円覚『日本で唯一犯罪が許される場所』(実業之日本社)