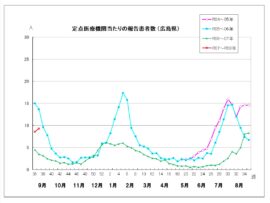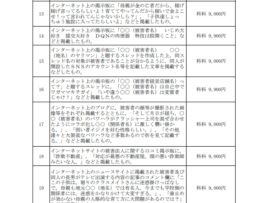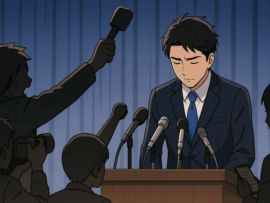富士山の山梨県側登山道「吉田ルート」では、今夏の開山に先立ち、登山者の安全を確保するための厳格な入山規制と指導が導入されました。特に「弾丸登山」と呼ばれる危険な夜間登山や、過剰な混雑を防ぐとともに、不十分な装備の登山者への対応が強化されています。2024年の夏山シーズンを前に、富士山レンジャーによる予行演習も行われ、安全対策の徹底が図られています。
 富士山吉田ルートの5合目で行われた予行演習で、軽装の登山者役に指導する富士山レンジャー
富士山吉田ルートの5合目で行われた予行演習で、軽装の登山者役に指導する富士山レンジャー
富士山吉田ルート、厳格化された入山規制と指導
6月、山開き前の吉田ルート5合目で行われた予行演習では、県富士山レンジャーの男性職員がサンダル履き、タンクトップや半ズボンといった軽装の登山者役3人に対し、「いまの格好だと(ゲートを)通すことができません」と毅然とした態度で入山を拒否しました。職員は必要な登山装備を売店で揃えるよう促し、準備が整うまで入山を認めませんでした。
山梨県は、2024年から入山料4000円を徴収する新たな規制を導入し、5合目の鉄製ゲートで午後2時から午前3時までの間、山小屋宿泊者と下山者以外の通行を制限しています。これは、富士山での遭難事故リスクを高める弾丸登山や、登山道の混雑による危険を避けるための重要な措置です。
昨年課題の「軽装登山者」対策と新条例の導入
昨年の規制導入初年度には、十分な装備を持たない軽装登山者が目立つという課題が浮上しました。富士山の山頂付近は夏でも氷点下になることがあり、防寒対策は必須です。天候が急変し、雨風を防ぐ装備がなければ、低体温症に陥る危険性も高まります。にもかかわらず、普段着やキャリーケースを持ったまま登山を試みる人々の様子が報じられ、安全確保の重要性が改めて認識されました。
この反省を踏まえ、山梨県は対応を強化。登山者に対し、防寒着、上下が分かれた雨具、登山に適した靴など、具体的な装備品の準備を義務付け、これに同意できない場合や装備が不足している場合は、県職員が入山を拒否できる新たな条例規則を設けました。
富士山レンジャーの権限強化と指導実績
さらに、山梨県は自然保護や安全指導を担う県富士山レンジャー3人を、昨年度までの会計年度任用職員から任期付きの正規職員として採用しました。これにより、レンジャーは県職員と同等の権限を持ち、より効果的な指導・対応が可能となりました。2017年からレンジャーを務める桜井美穂さんは、「明らかに登山に適さない格好や、天気が悪くなるのに無理に登ろうとする人を昨年より引き留めやすくなった」と、権限強化の効果を実感しています。
県によると、開山した7月1日からの1カ月間で、装備に関する指導を受けた登山者は630人に上りました。そのうち、上下が分かれた雨具を持たない登山者が535人と8割以上を占めています。
登山者の理解と協力:安全な富士登山へ
幸いにも、ほとんどの登山者は指導に従い、大きなトラブルは発生していないと報告されています。長崎幸太郎知事は8月の定例記者会見で、登山者が「(県職員の)指導に理解を示し、安全を確保した上で登山されている」と述べ、協力に感謝の意を表しました。
富士山の入山規制と安全対策の強化は、登山者の命を守り、世界遺産としての価値を保全するために不可欠です。適切な準備と規定への理解・協力が、安全で思い出に残る富士登山へと繋がります。
参考文献: