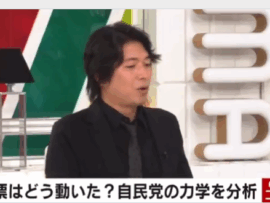2024年8月、イギリス海軍の最新鋭空母「プリンス・オブ・ウェールズ」が神奈川県の横須賀基地に姿を現しました。排水量6万5000トンを誇るこの巨大軍艦は、その大きさで海上自衛隊の護衛艦と並び立つ姿が注目を集めました。その後、東京港へ移動し、一部メディアには艦載機F-35Bステルス戦闘機が並ぶ甲板が公開され、その高性能ぶりが披露されました。このイギリス空母の日本寄港は、単なる友好訪問に留まらない、インド太平洋地域の安全保障環境における重要な戦略的メッセージを内包しています。
 横須賀基地に停泊するイギリス海軍の空母「プリンス・オブ・ウェールズ」と海上自衛隊の護衛艦
横須賀基地に停泊するイギリス海軍の空母「プリンス・オブ・ウェールズ」と海上自衛隊の護衛艦
最新鋭空母「プリンス・オブ・ウェールズ」の能力と日本展開の意義
「プリンス・オブ・ウェールズ」の最大の特徴の一つは、甲板に搭載されたF-35Bステルス戦闘機と、反り返ったスキージャンプ甲板です。これにより、F-35Bはわずか100メートルあまりの滑走で離陸が可能となります。この最新鋭の航空戦力を擁する空母が、なぜこのタイミングで日本を訪問したのでしょうか。その背景には、地域大国に対する明確な牽制と、日米英の連携強化という戦略的意図が読み取れます。フジテレビ特別解説委員の能勢伸之氏は、今回の訪問について「中国への牽制の思惑が垣間見える」と指摘しています。
中国牽制の明確な意図:歴史的記念日と南シナ海の戦略
「プリンス・オブ・ウェールズ」の日本滞在時期は、中国が日本との戦争勝利80周年を記念する大規模なパレードを9月3日に開催する直前でした。艦隊はパレード前日に日本を離れた後、第二次世界大戦中に南シナ海で日本軍によって撃沈された戦艦、初代「プリンス・オブ・ウェールズ」の追悼式典を海上自衛隊と共に実施する予定が組まれていました。能勢氏は、この追悼式典についてイギリス側が「この地域での協力にどれだけ真剣であるかを示すもの」としている一方で、「追悼式典と中国海軍のミサイル原潜が潜む南シナ海そのものに軍艦を送り込み、探りを入れることのどちらに真剣であるか、興味深いところだ」と述べ、南シナ海への展開が中国への強力なメッセージであることを示唆しています。
インド太平洋安定化への英国の貢献:米国が描く未来図
中国への牽制と同時に、イギリスは日本との防衛関係強化も進めています。寄港前には、「プリンス・オブ・ウェールズ」のF-35Bが、事実上の空母化が進む海上自衛隊の護衛艦「かが」の甲板に初めて着艦する訓練を実施しました。また、2025年にはイギリスとアメリカのF-35Bが日本国内の民間飛行場に緊急着陸する事案も発生しており、こうした際の救難態勢は、日英米を含む有志国が日本周辺に駆けつける能力に影響を与える可能性があります。
駐日アメリカ大使のグラス氏は、SNSで「大西洋を跨ぐ米英同盟がインド太平洋の平和と自由を守る」と発信しており、アメリカが描く新たな「青写真」が浮かび上がります。1980年代に15個の空母中心艦隊を目指したアメリカは現在11隻を保有していますが、同盟国であるイギリスが2隻、フランスが1隻と本格空母を運用しており、これらを合わせれば14隻となります。アメリカは、イギリスがアジアの安定の一翼を担うことで、インド太平洋地域における集団的な抑止力を強化する戦略を描いているのかもしれません。
結論
イギリス空母「プリンス・オブ・ウェールズ」の日本寄港は、単なる親善訪問以上の戦略的意味合いを持っていました。中国への牽制、歴史的背景を伴う南シナ海での存在感誇示、そして日本の海上自衛隊との連携強化は、インド太平洋地域における安全保障の重要性を改めて浮き彫りにしています。米英同盟がインド太平洋の平和と自由を守るというアメリカの構想の下、イギリスがこの地域で果たす役割は今後さらに拡大していくことでしょう。これは、国際社会における日英米の協力体制が、地域の安定に不可欠であることを示す明確なシグナルと言えます。
参考文献
- FNNプライムオンライン
- 能勢伸之(フジテレビ特別解説委員)