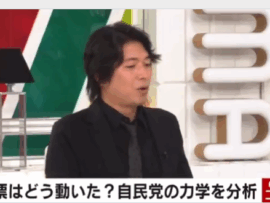最近、日本では新型コロナウイルス変異株「ニンバス」の流行拡大や「第12波」到来の報道が相次ぎ、一部医療機関ではマスク着用義務や面会制限の再開といった対応が見られます。しかし、2007年にスウェーデンへ移住し、カロリンスカ大学病院泌尿器外科に勤務する医師であり、日本泌尿器科学会専門医及びスウェーデン泌尿器外科専門医である宮川絢子博士の視点からは、こうした日本の反応に対して疑問を感じざるを得ないといいます。かつて「都市封鎖せず」という独自路線で世界的に注目されたスウェーデンでは、現在、新型コロナウイルスにどのようなアプローチが取られているのでしょうか。現地からの寄稿をもとに、その実情を詳しく解説します。
スウェーデン社会における新型コロナウイルスの位置づけ
スウェーデン社会において、新型コロナウイルスはもはや過去の出来事として忘れ去られており、ニュースの主要な話題となることもありません。感染の波についても、2022年末から2023年にかけての第5波までは数えられていたものの、それ以降は数えること自体に意義を見出さないという認識です。新型コロナウイルスは、今後も通常のコロナウイルスと同様に流行し続けるものと捉えられており、病院でも特別な扱いを受けることはなくなりました。
検査体制の変化と現状
日本では広く行われている新型コロナウイルス検査ですが、スウェーデンではその機会が極めて限定されています。以前は街中で見かけることもあった抗原検査キットも、現在ではほとんど姿を消しました。検査は、入院が必要な症状がある場合に大病院でスクリーニングとして実施されるか、あるいは感染に脆弱な人々が居住する高齢者施設で有症状者に対してのみ行われます。一般的な街の診療所で検査が実施されることはありません。
 スウェーデンの医療専門家が新型コロナウイルスに関するデータを分析する様子
スウェーデンの医療専門家が新型コロナウイルスに関するデータを分析する様子
症状発生時の標準的対応と治療
風邪のような症状がある場合、スウェーデンにおける標準的な対応は、医療機関を受診して検査をするのではなく、「常識を働かせ」自宅で療養することです。日本で設置されているような「発熱外来」はスウェーデンには存在しません。したがって、抗ウイルス薬の投与もクリニックレベルでは行われず、大病院でさえも、感染に脆弱な感染者のうち、ごく限られた患者に対してのみ適用されるにとどまります。
結論
宮川絢子博士の報告から明らかになるのは、スウェーデンが新型コロナウイルスを季節性インフルエンザや一般的な風邪ウイルスと同様の存在として捉え、社会全体でその対応を「日常化」させていることです。日本で現在も続く「波」の報道や特定の医療措置の再開とは対照的に、スウェーデンでは検査の限定化、自宅療養の推奨、そして医療現場での特別な扱いの終了といったアプローチが徹底されています。この異なる対応は、感染症に対する社会的な認識と公衆衛生戦略の多様性を示唆しており、私たちに新たな視点を提供しています。