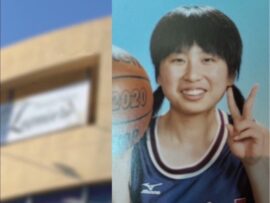イスラエルとパレスチナ。この二つの地域とその住民の間で続く紛争は、なぜこれほどまでに根深く、平和が訪れることの難しい状況にあるのでしょうか。その問いに答えるためには、現在の地政学的問題だけでなく、3000年以上にもわたる両者の複雑な歴史的背景を理解することが不可欠です。本稿では、宗教と政治の関係を専門とするカナダの学者の見解を参考に、この長きにわたる対立の種と歴史的経緯を簡潔に振り返ります。
「イスラエル」という名の起源と古代王国
「イスラエル」という名前が歴史上に初めて登場するのは、紀元前13世紀の終わり頃、エジプトに建立されたメルエンプタハ石碑においてです。この文脈では、特定の地名というよりも、当時の「カナーン」と呼ばれる地域に居住していた民を指す集合的な呼称として用いられていました。その後数世紀を経て、この肥沃な地域には、「イスラエル」と「ユダ」という二つの姉妹王国が形成されます。聖書によれば、これら二国に先立ち、両地域を統合する「イスラエル」と呼ばれる統一王朝が存在したとされています。しかし、紀元前722年頃、現在のイラクを中心とする広大なアッシリア帝国によってイスラエル王国は征服され、古代の地名としての「イスラエル」はここで一度姿を消します。
ユダ王国の存続と苦難の歴史
イスラエル王国が滅亡してからおよそ1世紀半後、姉妹国であるユダ王国もまた、その運命を辿ります。首都エルサレムは略奪され、ユダヤ教の中心であった壮麗なユダヤ神殿は破壊されました。この出来事により、ユダ国民の多くはバビロニアへと国外追放される、いわゆる「バビロン捕囚」を経験します。国外追放が終わり、約50年足らずでユダヤ人が故郷に戻ると、かつてのユダ王国の領土は、その後約7世紀にわたりユダヤ教の精神的な中心地として再興されました。しかし、紀元70年にはローマ人によって再建された第二神殿も再び破壊され、ユダヤ人の苦難は続きます。
 歴史的な対立が続くイスラエルとパレスチナ地域の荒涼とした風景
歴史的な対立が続くイスラエルとパレスチナ地域の荒涼とした風景
「パレスチナ」の誕生とアラブ人定住
紀元135年、ユダヤ人によるローマ帝国に対する大規模な蜂起が失敗に終わると、ローマ皇帝ハドリアヌスはユダヤ人をエルサレムから追放し、この都市と周辺の土地を「シリア=パレスチナ」と呼ばれる地域の一部とすることを命じました。この「パレスチナ」という名は、古代イスラエル人(ユダヤ人の祖先)の長年の敵であったペリシテ人の沿岸部の領土に由来するとされています。7世紀にイスラム勢力が中東地域を征服して以降、アラブ系の諸民族がかつての「パレスチナ」の地に定住し始め、その人口は増加の一途を辿ります。約90年間にわたる十字軍の支配という例外を除けば、この土地はその後1200年近くにわたりイスラム教徒の統治下にありました。この期間中もユダヤ人が完全に姿を消すことはありませんでしたが、人口構成としては圧倒的にアラブ人が多数を占める状況が続いたのです。
この地に深く刻まれた多様な歴史は、現代のイスラエルとパレスチナのアイデンティティ、土地に対する主張、そして終わりのない紛争の根源を形成しています。平和への道は、この複雑に絡み合った歴史的経緯を深く理解することから始まるのかもしれません。
情報源: Daniel Miller (courrier.jp via Yahoo News)