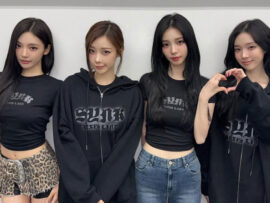2022年2月24日に勃発したロシアによるウクライナ侵攻は、既に42カ月間続き、その戦闘期間は朝鮮戦争(37カ月)を超えました。この長期化する紛争の根底には、深く根ざした民族問題が存在しています。ソ連史の最高権威者であり、米カリフォルニア大学バークレー校(UCバークレー大)歴史学科名誉教授のユーリ・スリョースキン氏は、旧ソ連の民族問題を長年研究してきました。自身もユダヤ系とウクライナ系の血を引くスリョースキン氏は、ロシアが西欧文明との「離婚」という過程にあり、ロシア・ウクライナ戦争がその動きをさらに加速させていると指摘します。ソウル大学の招きで韓国を訪れたスリョースキン氏が、この複雑な紛争の歴史的・民族的背景について語りました。
ソ連の民族政策とスターリンの役割
ヨシフ・スターリンは、1922年にソ連共産党書記長となる以前、民族人民委員会の委員長を務め、ソ連の民族政策の大部分を主導しました。ソ連は歴史上初めて、多民族国家として構想された独特の実験国家でした。その領土と市民は全て民族的に規定され、当初は土着化政策が推進されました。これは民族のエリートを育成し、民族の言語や文化を奨励するものでした。しかし、1930年代に入ると、中央集権を通じた近代化のために、公的に認められる民族単位の数が減らされ、ロシア語が公用語として採択されました。それでも「民族-領土連邦」という原則は堅持され、最終的にソ連はこの連邦共和国の境界線に沿って崩壊を迎えることになります。
ウクライナ問題に影響を与えたソ連の遺産
ソ連の民族政策は、ウクライナ問題に特有の影響を及ぼしました。一つは、1930年代の大飢饉(ホロドモール)がウクライナに甚大な被害をもたらし、これがウクライナの民族主義的な争点として深く刻み込まれたことです。二つ目に、ウクライナ人とロシア人は文化的に非常に近く、両集団を明確に区別することが難しいという点が挙げられます。特にウクライナ東部は事実上、ロシア語が主要言語の地域であり、西に進むにつれて言語や文化が変化します。例えば、かつてオーストリア=ハンガリー帝国の一部であったガリツィア(ウクライナ西部)は、言語と宗教において全く異なる文化圏を形成していました。ロシア人とウズベキスタン人が明確に区別されるのに対し、ロシア人とウクライナ人の間には曖昧な境界が存在するのです。
 米UCバークレー大学のユーリ・スリョースキン名誉教授が、ロシア・ウクライナ戦争における民族問題の深層についてインタビューに応じる様子
米UCバークレー大学のユーリ・スリョースキン名誉教授が、ロシア・ウクライナ戦争における民族問題の深層についてインタビューに応じる様子
最後に、ウクライナの国境は、その歴史的な流動性と文化的な近接性から、常に論争の対象となりやすいという特徴があります。ニキータ・フルシチョフがクリミア半島をウクライナ共産党に「贈与」した事例は、その代表的な例と言えるでしょう。
プーチン大統領が戦争を始めた真の理由
プーチン大統領は、北大西洋条約機構(NATO)がウクライナへと拡張し、ウクライナ政府が東部のロシア語使用人口を差別していると認識していました。彼は、「2014年に行動しなかったのは失敗だった。ウクライナは事実上NATO加盟国へと変化した。したがって、今行動しなければならない」と考えた可能性が高いとスリョースキン氏は分析します。
ロシアの膨張主義と二つの帝国衝突
ロシアは、歴史的に帝国としての性質を持ち、他の強大国からの尊重を要求し、国家の利益と安全保障上の懸念を自国の領土の向こう側まで拡大しようとする傾向があります。ウクライナのような国に対しては、干渉する権利があると考える点で、米国と類似しているとも言えます。今回の戦争は、米国を中心とする「世界的帝国」と、地域的で比較的弱く見える「ロシア」という二つの帝国間の衝突であるとスリョースキン氏は見解を述べます。しかし、ロシアは非常に大きく、核兵器を保有する強力な国であるため、衛星国に転落することはありません。元々、西側中心の国際安全保障体制にロシアを完全に統合することは困難な課題でした。
ロシア国民がプーチン大統領を支持する背景
ロシアの多くの専門職、知識人、エリート層は、道徳的・政治的な理由から戦争に反対し、既に海外へと流出しています。しかし、国内に残った大部分のロシア国民は、プーチン大統領と国家を中心に団結している状況です。スリョースキン氏は、今回の戦争が「内戦」としての性格を強く帯びていると指摘します。大多数のロシア国民は、政府が提示する「NATO拡張の危険性」や「ウクライナ政権の急進的民族主義」という公式説明に共感し、それを受け入れています。
西側諸国が予測するような、プーチン大統領がウクライナに続いて他国へ侵攻するという見方は、説得力が弱いとスリョースキン氏は考えています。ウクライナは文化的にも近く、西側の影響力拡大の動きが遅かったため、ロシア大統領府(クレムリン)がまだ対抗可能だと感じた特殊な事例です。これに対し、エストニア、ラトビア、リトアニアのバルト三国は、完全に異なる民族であり、既に西側体制に編入されています。ウクライナの運命だけが、依然として不確かであったというのが、スリョースキン氏の分析です。
結論
ユーリ・スリョースキン教授の分析は、ロシア・ウクライナ戦争が単なる領土紛争ではなく、ソ連時代の民族政策の遺産、ロシアの帝国としての歴史的性向、そして西側との関係における「離婚」プロセスが複雑に絡み合った結果であることを示唆しています。民族的曖昧さや流動的な国境、そして異なる文明圏としての認識が、紛争の長期化とロシア国民の支持形成に大きく影響しています。この深い歴史的・文化的背景を理解することは、現在の地政学的状況を読み解く上で不可欠です。
参考資料
- 中央日報 日本語版 2025年9月9日配信記事