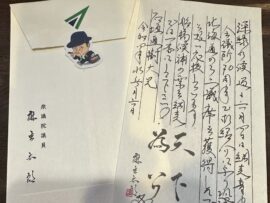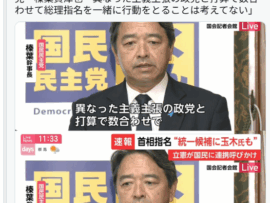「もう歳だから無理」「老害扱いされるから黙っておこう」。もしあなたがそう感じ、年齢を理由に物事を判断しているなら、あなたの脳は静かに老化のプロセスに入りつつあります。しかし、脳科学者の茂木健一郎氏によると、年齢にとらわれずに行動し続ければ、脳は何歳からでも成長を続けることができると言います。本稿では、茂木氏の著書『60歳からの脳の使い方』から、脳のメカニズムと、年齢による自己制限がもたらす弊害について深く掘り下げていきます。
 年齢にとらわれず成長し続ける脳のイメージ図
年齢にとらわれず成長し続ける脳のイメージ図
年齢による自己限定が脳の成長を阻害するメカニズム
物事を年齢で判断することの最大の弊害は、年齢という固定観念に縛られ、その人が本来持つ可能性や才能を見過ごしてしまう点にあります。人間の脳は、年齢に関係なく新しい挑戦や学びを通じて常に成長する能力を持っています。これこそが脳の持つ素晴らしい特性です。
しかし、「この年齢だからもうダメだ」と自ら制約を設けてしまうと、脳内に「学習性無力感」という現象が生じます。学習性無力感とは、繰り返し避けられないストレスや苦痛を経験することで、「自分の行動では状況を変えられない」と学習し、努力や回避行動を放棄してしまう心理的状態を指します。例えば、ラットを使った実験では、回避不能な電気ショックを与えられた後、電気ショックを回避できる状況に置かれても、「逃げても無駄だ」と学習してしまい、逃避行動を示さなくなることが観察されています。
これと同様のことが人間にも起こり得ます。「これ以上行動しても意味がない」と感じて学習性無力感が生まれると、本来持っているポテンシャルを発揮できなくなります。これにより自信を失い、「自分には何もできない」という負のスパイラルに陥ってしまうのです。自ら勝手に制約を設け、能力を低下させてしまうことは、非常にもったいないことだと言えるでしょう。
茂木氏自身は、人と接する上で年齢を気にしたことはほとんどなく、常に「エイジレス」という考え方を大切にしていると述べています。エイジレスとは、単に年齢にとらわれないという表面的な意味合いだけでなく、「年齢によって生じる壁や差別がない生き方」を目指すというものです。この考え方を持つことで、「あの人は年配だから頭が固い」「あの人は若いから考えが浅い」といった余計な偏見を持たずに人と接することができ、何よりも自分自身が年齢に縛られずに自由に活動できると茂木氏は強調します。
「老害」という言葉が持つ社会的弊害と本質的な問題
年齢に対する差別意識が強い日本社会において、特に特徴的な表現として「老害」という言葉が挙げられます。この言葉は、一般的に、年齢を重ねた人が周囲に対して否定的な影響を与えている状況で使われます。しかし、茂木氏は「老害」という言葉を好ましくないと語ります。なぜなら、この言葉は、その問題の背後に隠れている本質的な背景を見えづらくしてしまうからです。
例えば、70代の男性が電車内で若者に暴行を加える事件が発生した場合、「高齢者はすぐキレるから困る」と、年齢を原因として短絡的に片付けてしまう傾向があります。しかし、過去には20代の若者が駅員に対して暴言を吐いたり、暴力的な態度を取ったりした事件も多々あります。若者が同様の暴力事件を起こした場合、年齢を理由に問題を説明することは稀です。代わりに、個人の性格、生育環境、ストレス状況などが背景として分析されるのが一般的です。
本来であれば、年齢にとらわれず、暴力的な態度や問題行動を引き起こす背景には何があるのかを、より深く掘り下げて分析することが不可欠です。「年を取ると仕方ない」と年齢でひとくくりにしてしまうことは、真の原因を見逃し、問題解決を先送りすることに他なりません。
また、日本社会において「老害」という言葉が使われる背景の一つには、上の世代が組織内の重要なポジションを長期間占め続ける現象も存在します。これが、若い世代の昇進やキャリア発展を妨げる要因となり、世代間の摩擦や不満を生むことがあります。このような状況も、「老害」という言葉が安易に使われる土壌となっている可能性がありますが、その本質は年齢そのものではなく、組織構造や個人の能力評価システムといったより複雑な問題にあると考えるべきです。
まとめ:年齢を超えた可能性と本質を見つめる社会へ
茂木健一郎氏が提唱する「エイジレス」な考え方は、私たち自身の脳の可能性を最大限に引き出すだけでなく、社会全体における年齢に対する固定観念を見直すきっかけを与えてくれます。年齢を理由に自らを限定することは、学習性無力感を生み出し、脳の成長を止めることにつながります。また、「老害」といった言葉で安易に問題を片付けることは、その背後にある真の社会構造や個人の問題を見過ごし、建設的な解決を遠ざけてしまいます。
年齢にとらわれず、常に学び、挑戦し続ける姿勢が、個人の豊かな人生と、より公平で理解し合える社会を築く鍵となります。私たちは、表面的な年齢ではなく、個々の能力、経験、そして行動の背景にある本質的な要因に目を向けるべきです。脳は何歳からでも成長し、社会もまた、年齢を超えた多様な価値観と可能性を受け入れることで、より豊かに発展していくことができるでしょう。
参考文献
- 茂木健一郎. (2025). 『60歳からの脳の使い方』. 扶桑社.
- Yahoo!ニュース (2024年某月某日). 「おじさんだからできないよ」と脳が老化…茂木健一郎が断言「何歳からでも成長し続ける」. https://news.yahoo.co.jp/articles/6a6016cb151d8c2ae1fdb458c033656af58e8c59
- ダイヤモンド・オンライン. (参照元記事).