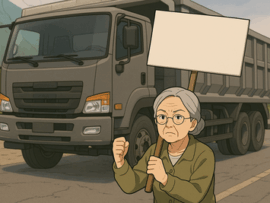[ad_1]
昭和56年放送開始の連続ドラマから平成14年のスペシャルまで、長きにわたり愛された「北の国から」。現在、有料放送の「日本映画専門チャンネル」で高画質の「デジタルリマスター版」が放送され、またも人気を博している。連ドラ開始当初、大きな話題にはならなかったのに、やがて国民的な人気を得るに至った。撮影開始から40年が経過する今、関係者らが作品を振り返る。(兼松康)
脚本の倉本聰が北海道・富良野に移住したのは昭和52年。「寒暖差の激しいところ、自然林のあるところを北海道中、探した。僕が来た頃は、冬と夏の気温差が70度ぐらいあった」という。もともと東京生まれの倉本。自ら望んだ移住だったが、「最初の2~3カ月は自然に試された感じで。ひどい鬱になった」と振り返る。
自然に親しみ、やがてそんな土地を舞台にドラマを書くことになった倉本。黒板家の五郎(田中邦衛)、純(吉岡秀隆)、蛍(中嶋朋子)が富良野へ移住してからが描かれたが、その背景の設定は後になって作られた。黒板家のルーツは徳島の蜂須賀藩の家老、稲田家にあり、そこから北海道・静内地方へ移った末裔(まつえい)というものだ。
人物の来歴を作ることで「ドラマにした際の“化学反応”があり、面白くなる」というのが倉本の持論。例えば、スペシャルの「’84夏」で、父子3人でラーメンを食べながら、純が丸太小屋の火事について自身の責任を告白するシーン。早く店を閉めたがるラーメン店の女性店員(伊佐山ひろ子)が、食べかけの器を片付けようとする場面で、五郎が「まだ子供が食ってる途中でしょうが!」と激高する有名な場面だが、倉本はここにも、表には描かれていない女性店員の設定を用意していた。
「子供が2人いて、早く帰らないと預けている先にも迷惑がかかる」という設定で、「彼女には彼女の理屈がある。生活も履歴も全く違う人物がぶつかることでの化学反応。それを考えるのがドラマの面白さ」と話す。父子の大切な時間を邪魔する無粋な店員にしか見えないシーンもまた異なる味わいが出てきそうだ。
[ad_2]
Source link