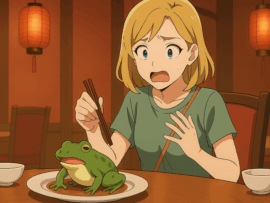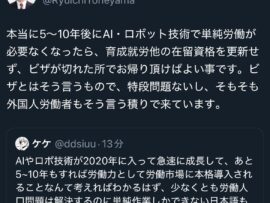[ad_1]

収束の気配を見せない新型コロナウイルスは、後継者不足などで事業承継に不安を抱えてきた伝統産業や、中小企業の経営者らが事業をたたむ引き金になりつつある。日本で数少ない三味線メーカー、東京和楽器(東京都八王子市)もまさに廃業の危機に直面している。芸術文化・エンターテインメント業界が活動再開に向けて動き出す一方、その足元を支える技術の中には、商業的に成り立ちにくいものも少なくない。専門家は「芸を支える土台がなくなれば、いずれは文化そのものが廃れる」と警鐘を鳴らす。 (文化部 石井那納子)
コロナ禍で注文ゼロ
文楽や歌舞伎などの古典芸能、地域に根付く民謡に欠かせない三味線。東京和楽器はその基本となる胴と棹(さお)、糸巻きを作る数少ない国内メーカーだ。代表を務める大瀧勝弘さん(80)の祖父が、明治18(1885)年に東京・深川で創業した三味線の胴屋(どうや)を前身とする。
従業員18人、国内シェア5~6割を占める最大手で、10年ほど前までは民謡ブームに支えられ年間約800挺(ちょう)を生産していたという。近年は年間400挺程度まで落ち込んだところに、コロナ禍が追い打ちをかけた。演奏会やイベントは軒並み中止となり、4~5月は三味線の新調や修理の注文が止まった。
大瀧さんは借金などで従業員の賃金を工面してきたが、「小規模事業者持続化補助金などで当座をしのいだところで将来は明るくない。倒産するよりも、経営余力があるうちに廃業するほうがいいだろうと話し合った」と明かす。現在は同社の危機を知った関係者から事業継続の方策を探る動きも出ているといい、「芸事に理解ある人のもとで技術を残せれば」と存続に一縷(いちる)の望みをかける。
業界取り巻く負のループ
全国邦楽器組合連合会の推計では、昭和45年には1万4500挺あった三味線の国内製造数が、平成29年には1200挺まで減った。背景には花柳界の衰退、習い事の多様化、民謡ブームの低迷による演奏人口減少が指摘される。
材料の枯渇も深刻だ。三味線の棹に使われる「紅木(こうき)」、糸巻きや撥(ばち)の材料となる「鼈甲(べっこう)」「象牙」もワシントン条約や動物愛護の立場から、現在は輸入禁止か、輸入が厳しく制限されている。
三味線は楽器であると同時に、伝統工芸品の側面も持つ。東京都の伝統工芸品に指定されている東京三味線の一部には、東京和楽器などメーカーから仕入れた胴や棹を組み立て、皮や糸を張って楽器として完成させているものもある。指定は職人の技術保護の一助になるものの、都によると、メーカーのつくった素材や技術は対象になっていないという。
この間、邦楽器業界は国に働きかけ、24年度以来、中学校の音楽教育での邦楽器必修化を実現させた。製造現場では材料として代替品の活用が進み、大瀧さんらは現代の住宅事情にも配慮した練習用サイレント楽器なども考案して、三味線に触れる機会を増やそうと試みてきた。
横浜市の長唄の三味線教室に通う高田朱美さん(47)は「普段は小売店としか接点がなく、メーカーの苦境は初めて知った。奏者自身も楽器がどのように作られているのか関心を持たなければ、知らないうちに技術が消え、伝統の音色が失われかねない」と戸惑いを隠せない。
市場任せでいいのか
大瀧さんは「複合的な要因があるなかで、新型コロナが廃業の踏ん切りをつけさせた」と話す。これは事業承継に不安を抱えてきた中小企業や、衰退傾向にある業種の経営者らにも共通し、民間信用調査会社の東京商工リサーチは、経営者が自主的に事業をたたむ休廃業・解散の件数が、今年は5万件を超えるのではないかと警戒感を強める。
コロナ禍では、日本の文化を支えてきた企業や技術でさえも消えてしまうものなのか。
民主党政権で官房副長官を務めた松井孝治・慶応義塾大学教授(統治機構論)は、「全てを市場原理に任せてはいけない」と指摘する。多くの政策決定過程に携わり、文化芸術に造詣が深いことでも知られる松井氏。三味線が活躍する歌舞伎や文楽は日本固有であることを例にあげ、「芸を支える技術が失われればいずれは文化そのものが消える。どれだけ歌舞伎や文楽が外国人に熱狂的に支持されても、支える技術が廃れてしまえば『オリジナル』がなくなってしまう」と危ぶむ。
一方で、行政が支援に取り組むためには、それに見合う価値があるか選択を迫られることも指摘。「文化庁は見極める目を持った技芸員の養成に力を入れるなど、それぞれがなすべきことを考える必要があるのではないか」と語った。
[ad_2]
Source link