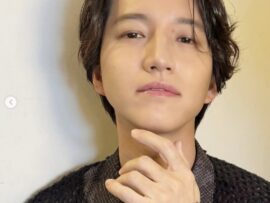日本では火葬が一般的ですが、イスラム教では土葬が義務付けられています。そのため、日本で暮らすイスラム教徒にとって、土葬墓地の確保は大きな課題となっています。この記事では、大分県日出町で計画されたイスラム教徒の土葬墓地が頓挫した事例を通して、日本の多文化共生社会における課題と展望を探ります。
土葬をめぐる現状:イスラム教徒の切実な願い
イスラム教では、故人を土に還す土葬が宗教上の義務とされています。しかし、日本では土葬のできる墓地が非常に限られています。関東地方には土葬可能な霊園が存在しますが、九州や中国地方などの地域では、土葬墓地はほとんどありません。そのため、これらの地域で暮らすイスラム教徒は、高額な費用をかけて遺体を関東まで搬送するケースも少なくありません。
 埼玉県本庄市の土葬可能な霊園。遠方からも遺体が搬送されている。
埼玉県本庄市の土葬可能な霊園。遠方からも遺体が搬送されている。
別府ムスリム協会代表のカーン氏は、「日本は第二の母国」と語る一方で、土葬墓地の確保問題については強い焦燥感を抱いています。カーン氏は、「一刻も早く地元で土葬ができる場所を見つけ、根本的に問題を解決したい」と訴えています。
日出町の土葬墓地建設計画:住民の反対と頓挫
2018年、別府ムスリム協会は信者向けの土葬墓地建設を目指し、大分県日出町に土地を確保しました。「九州地方では初」となるムスリム向けの土葬墓地として、この計画は大きな注目を集めました。建設予定地は人里離れた山中で、環境への影響も少ないと考えられていました。
 別府ムスリム協会代表のカーン氏。日本国籍を取得し、日本で教壇に立っている。
別府ムスリム協会代表のカーン氏。日本国籍を取得し、日本で教壇に立っている。
しかし、計画が進むにつれて、地元住民から不安の声が上がり始めました。水質汚染や地価下落への懸念、さらには宗教的な偏見も反対理由として挙げられました。別府ムスリム協会は住民との対話を重ね、代替案として町有地を建設候補地とするなど、妥協点を探りましたが、最終的には2024年の町長選挙で土葬墓地建設反対を掲げた候補が当選し、計画は頓挫しました。
 別府ムスリム協会が当初建設を予定していた日出町の土地。町の中心部から離れた山地にある。
別府ムスリム協会が当初建設を予定していた日出町の土地。町の中心部から離れた山地にある。
多文化共生社会の実現に向けて:理解と歩み寄りが必要
日出町の事例は、日本で暮らす外国人、特に宗教的少数派が直面する困難を浮き彫りにしています。 多文化共生社会を実現するためには、相互理解と歩み寄りが不可欠です。行政は、住民の不安に寄り添いつつ、宗教的少数派のニーズにも配慮した政策を推進する必要があります。また、私たち一人ひとりが、異なる文化や宗教への理解を深め、共存していくための努力を続けることが重要です。
まとめ:土葬問題から考える日本の未来
土葬問題は、単なる墓地の問題ではなく、日本の多文化共生社会のあり方を問う重要なテーマです。今後、日本に暮らす外国人はさらに増加すると予想されます。宗教や文化の違いを乗り越え、真に多様性を受け入れる社会を築き上げるためには、私たち一人ひとりの意識改革が求められています。