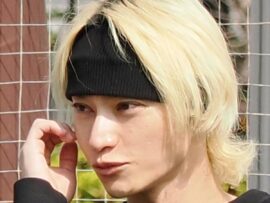25年前、愛娘を理不尽に奪われた遺族。新たな制度「心情等伝達制度」を利用し、加害者へ思いを伝えようと試みるも、返ってきたのは想像を絶する残酷な言葉でした。それでもなお、制度利用を続けるその背景には、一体何が? 本記事では、制度利用者の声と長年被害者支援に携わる保護観察官の視点から、この制度の意義と課題、そして犯罪被害者遺族が抱える苦悩に迫ります。
繰り返される問いかけ、届かぬ思い
 横浜市の渡邉保さん
横浜市の渡邉保さん
2023年12月にスタートした「心情等伝達制度」。刑務所に服役する加害者に対し、被害者やその家族・遺族が心情を伝えることができる、画期的な制度です。横浜市在住の渡邉保さん(76歳)は、この制度を既に2度利用し、3度目の利用も検討しています。2000年、当時22歳だった長女をストーカー加害者に殺害された渡邉さんにとって、この制度は「犯罪被害者がようやく手にした権利」なのです。
加害者からは、過去の出来事を「なかったことにしたい」という、被害者を深く傷つける言葉が返ってきました。しかし、渡邉さんは制度利用を諦めません。「加害者の更生の実態を知ることができた」と、制度の意義を強調します。長年にわたる苦悩、そして加害者への問いかけは、今もなお続いています。
20年以上前の悲劇、今も続く悪夢
2000年10月、渡邉さんの長女は中学校時代の同級生に殺害されました。加害者は長年にわたりストーカー行為を繰り返しており、事件当日、帰宅途中の長女をRV車ではね、農地に連れ込み、包丁で刺殺するという残忍な犯行に及んだのです。
2003年、加害者は自首。裁判では無期懲役の判決が下されました。しかし、法廷での加害者の態度は、遺族にとって更なる苦痛となりました。「お前が迎えに行かなかったから娘は死んだんだ」という心ない暴言。この言葉は、渡邉さんの心に深い傷を残しました。
制度の意義と課題、保護観察官の視点
 事件現場の様子
事件現場の様子
「心情等伝達制度」は、犯罪被害者支援の大きな一歩と言えるでしょう。しかし、制度の運用には課題も残されています。例えば、加害者からの返答の内容や時期、そして加害者の更生への影響など、検証すべき点は少なくありません。
長年犯罪被害者支援に携わってきた保護観察官のA氏(仮名)は、「加害者にとって、被害者の心情に直接向き合うことは更生への重要な契機となる可能性がある」と指摘します。一方で、「被害者にとっては、加害者からの返答が更なる苦痛となる場合もある」とし、慎重な対応が必要だと強調します。
被害者支援の未来に向けて
犯罪被害者支援は、社会全体の責任です。「心情等伝達制度」のような新たな取り組みは、被害者とその家族の心のケア、そして加害者の更生を促す上で重要な役割を担っています。
今後、この制度がより効果的に機能するためには、関係機関の連携強化、そして被害者一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかな支援体制の構築が不可欠です。犯罪のない社会の実現に向けて、私たちは共に考え、行動していく必要があります。