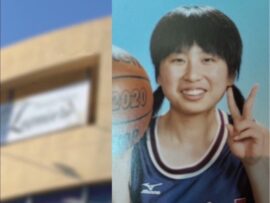教員の精神疾患による休職者数が過去最多を更新し、深刻な問題となっています。特に若手教員の間で増加傾向にあり、その背景には、いじめ対応の難しさや保護者との関係悪化などが挙げられています。この記事では、現役教員のリアルな声を通して、教育現場の現状と課題を探ります。
いじめ対応の難しさ:ゲームでの仲間外れも「いじめ」?
東京都内の公立小学校に勤務する30代の女性教員は、2年前のいじめ対応がきっかけで精神的に追い詰められました。クラスで起きたゲームでの仲間外れに対し、いじめとして対応したところ、加害児童の保護者から「ゲーム中の仲間外れはいじめではない」とクレームを受け、親子関係が悪化。その後、学校に行きたくないと思うようになり、心療内科を受診した結果、「抑うつ状態」と診断され、2ヶ月間の休職を勧められました。
 alt_text
alt_text
彼女は、悪夢を見るようになったといいます。子どもたちが教室で騒いでいても静まらない夢や、何度注意しても同じことを繰り返す子どもの夢など、自分が怒鳴りつけている夢ばかり見るようになったそうです。
増加する若手教員の精神疾患:4人に1人が「児童・生徒への指導」で不調
文部科学省の調査によると、2023年度に精神疾患で病気休職した教員は7119人と過去最多を記録。そのうち約半数は20代〜30代の若手教員です。要因別に見ると、最も多かったのは「児童・生徒への指導に関する業務」で、全体の約4分の1を占めています。特にいじめ指導において、保護者との対応に苦慮するケースが多く、若手教員がメンタルヘルス不調に陥る一因となっています。
教育心理学専門家の佐藤先生(仮名)は、「現代のいじめは複雑化しており、学校現場だけで解決することは困難なケースが増えています。保護者との連携が不可欠ですが、教員への負担が大きくなっているのも事実です」と指摘します。
教員のメンタルヘルス対策:多忙化解消とサポート体制の強化が急務
教員の精神疾患による休職増加の背景には、長時間労働や複雑化する学校業務など、様々な要因が絡み合っています。教員の多忙化を解消し、精神的な負担を軽減するための対策が急務です。
具体的には、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど専門スタッフの配置拡充、教員同士が気軽に相談できる体制づくり、保護者との良好な関係構築のための研修などが挙げられます。また、ICTを活用した校務の効率化も有効な手段と言えるでしょう。
教育現場の最前線で働く教員たちが、安心して子どもたちと向き合えるよう、社会全体で支えていく必要があります。