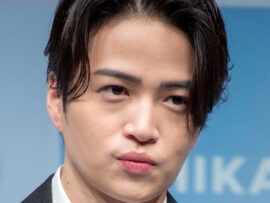アメリカでは、1セント硬貨の製造コストが額面を上回っていることが長年の課題となっています。2025年、トランプ前大統領はソーシャルメディアでこの「無駄遣い」を指摘し、鋳造停止を指示したことが話題となりました。この記事では、1セント硬貨をめぐる議論、製造コストの実態、そして各国の対応について詳しく解説します。
1セント硬貨:製造コストと無駄遣いへの懸念
トランプ前大統領は、1セント硬貨の製造コストが2セントを超えていることを「無駄」と批判し、鋳造停止を指示しました。政府効率化省も同様に、1セント硬貨を無駄の象徴として挙げています。キャッシュレス化が進む現代において、少額硬貨の利用頻度は減少しており、コスト超過の現状は疑問視されています。
 alt_text
alt_text
アメリカ造幣局のデータ:1セント硬貨の赤字の実態
アメリカ造幣局のデータによると、2024会計年度には31億7200万枚もの1セント硬貨が製造され、1枚あたり2.69セントの赤字が発生しました。年間の赤字額は約8530万ドルにものぼります。一方で、50セント、25セント、10セント硬貨は黒字となっており、造幣局全体では約9950万ドルの利益を計上しています。
各国の対応:1セント硬貨の廃止事例
カナダ、オーストラリア、ニュージーランドでは既に1セント硬貨の鋳造が停止されています。これらの国では、小売価格の端数を切り上げる、切り捨てるなどの対応策が取られています。日本では、貨幣の製造原価は非公開とされており、国民の貨幣に対する信認維持や偽造防止の観点から公表されていないとのことです。通貨制度専門家の山田一郎氏(仮名)は、「製造コストの透明性を高めることで、国民の理解と議論を深める必要がある」と指摘しています。
日本の現状:円貨製造原価の非公開
日本の造幣局は、円貨の製造原価を公表していません。これは、国民の貨幣に対する信認維持や偽造防止といった理由によるものです。しかし、製造コストの透明化を求める声も上がっており、今後の議論が注目されます。
まとめ:1セント硬貨の未来
1セント硬貨の製造コスト超過は、アメリカだけでなく世界的な課題となりつつあります。キャッシュレス化の進展とともに、少額硬貨の必要性も変化していくでしょう。各国がどのように対応していくのか、今後の動向に注目です。