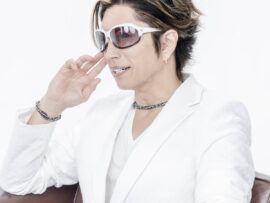日本のインフラ、特に下水道を取り巻く状況は、決して楽観視できるものではありません。道路陥没事故の増加や、水道料金の高騰など、私たちの生活に直結する問題が山積しています。この記事では、老朽化する下水道の現状と、私たちが直面する課題について詳しく解説します。
老朽化が招く道路陥没の恐怖
2025年1月28日、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故は、記憶に新しいところです。直径約5メートル、深さ約10メートルという巨大な穴にトラックが転落するという衝撃的な出来事は、下水道老朽化の深刻さを改めて突きつけました。事故原因は、老朽化した下水道管の腐食とみられています。
下水道管の耐用年数は一般的に50年と言われていますが、全国約49万キロの下水道管のうち、既に耐用年数を超過しているものが2022年時点で約3万キロに達しています。さらに2032年には約9万キロ、2042年には約20万キロにまで増加すると予測されており、道路陥没の危険性はますます高まっています。
 alt_text
alt_text
2022年には、下水道老朽化による道路陥没が約2600件も発生しています。このまま放置すれば、私たちの安全は脅かされ、甚大な被害をもたらす可能性があります。「下水道管路技術研究会」の専門家、山田一郎氏(仮名)は、「早急な対策が不可欠です。老朽化対策を怠れば、取り返しのつかない事態を招くでしょう」と警鐘を鳴らしています。
下水道だけではないインフラ老朽化問題
深刻な老朽化問題は、下水道だけにとどまりません。上水道管の破裂や漏水事故も年間2万件を超えており、こちらも危機的な状況です。水道管の法定耐用年数は40年ですが、2020年には全国の水道管の約2割が既に耐用年数を超過しています。
さらに、耐震適合率を満たした水道管はわずか4割に過ぎません。能登半島地震の際にも、水道管の耐震化の遅れが住民生活に深刻な影響を与えました。水道インフラの老朽化対策は、私たちの生活を守る上で喫緊の課題と言えるでしょう。
維持管理費用の高騰と水道料金値上げの懸念
下水道管の維持管理・更新費用は、2028年には1.2兆円に達すると試算されています。この費用は主に住民の下水道使用料で賄われますが、国土交通省の調査によると、下水道事業者の8割が使用料だけでは必要な経費を賄えていないのが現状です。
上水道も同様に、事業費用や水道管の耐震化・更新費用は水道料金で賄われています。人口減少が進む中、これらのインフラを維持していくためには、水道料金の値上げは避けられないとされています。
人口減少が加速させる水道料金の高騰
コンサルティング会社のEY Japanと水の安全保障戦略機構事務局が発表したレポートによると、2046年の水道料金は2021年度と比較して平均48%も上昇すると予測されています。
全国平均の水道料金(平均的な使用水量の場合)は、2021年は月額3,317円でしたが、2046年には4,895円にまで上昇すると見込まれています。地域による料金格差も拡大し、2046年度には最高額と最低額の差がなんと20.4倍にも広がると予測されています。
人口減少は、インフラ維持の負担を増加させる大きな要因です。利用者が減少する一方で、インフラの維持管理費用は変わりません。そのため、一人あたりの負担が増加し、水道料金の高騰につながるのです。
未来への課題:持続可能なインフラ整備に向けて
老朽化するインフラを放置すれば、私たちの生活基盤は崩壊の危機に瀕します。安全な暮らしを守るためには、早急な対策が必要です。国や地方自治体は、効率的なインフラ整備計画を策定し、持続可能な社会の実現に向けて取り組む必要があります。私たちも、日頃からインフラの重要性を認識し、未来への投資として積極的に協力していく必要があるでしょう。