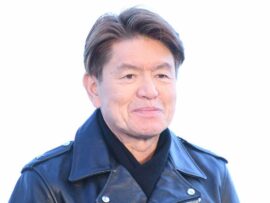京都市が、琵琶湖の水源保全に対する感謝の気持ちとして滋賀県に支払っている「琵琶湖疏水感謝金」。2025年度からの10年間も、年間2億3000万円を継続して支払うことが決定しました。 京都市民にとって、琵琶湖の水はまさに生命線。今回は、この感謝金の背景にある歴史や、両自治体の協力関係について深く掘り下げてみましょう。
琵琶湖疏水と京都市の深い繋がり
 alt京都市の水道水の99%を支えている琵琶湖の水。その水は、琵琶湖疏水を通じて京都市内に供給されています。写真:大津市の第2疏水取水口
alt京都市の水道水の99%を支えている琵琶湖の水。その水は、琵琶湖疏水を通じて京都市内に供給されています。写真:大津市の第2疏水取水口
琵琶湖疏水は、明治時代に建設された画期的な水路です。この疏水のおかげで、京都市は安定した水源を確保し、都市としての発展を遂げることができました。 現在も、京都市民の生活用水や産業用水の大部分を琵琶湖の水が担っており、その重要性は計り知れません。 疏水完成以前、水不足に悩まされていた京都。疏水建設は、まさに京都の命運を左右する一大プロジェクトだったと言えるでしょう。
感謝金の始まりと歴史的背景
大正3年(1914年)、当時の河川法に基づき、京都市は滋賀県に「水利使用料」として年間1600円の支払いを開始しました。その後、法改正で使用料の支払いが不要になった後も、京都市は水源保全への感謝の気持ちを表すため、寄付という形で支払いを継続。終戦後の昭和22年(1947年)からは、「琵琶湖疏水感謝金」という名称になりました。
感謝金の変遷と金額決定の仕組み
感謝金の金額は、両自治体間の協議によって、主に10年ごとに改定されています。社会情勢や物価の変動を考慮し、段階的に増額されてきました。1970年代後半には年間9000万円、1995年度からは年間2億2000万円、そして2015年度からは年間2億3000万円となっています。 今回の見直しでは、物価や人件費の高騰による琵琶湖保全コストの増加などを考慮し、2034年度まで現在の金額を据え置くことで合意しました。
琵琶湖保全への取り組みと感謝金の意義
滋賀県は、琵琶湖の水質保全や水草の刈り取り、森林保全など、多岐にわたる取り組みを実施しています。2024年度の予算は395億円にのぼり、その財源の一部として感謝金が活用されています。 京都市上下水道局の経営企画課長(架空の人物)である山田太郎氏は、「琵琶湖の水がなければ、京都市の水道事業は成り立ちません。感謝金は、単なる金銭的な援助ではなく、京都市民の感謝の気持ちの象徴です」と語っています。 水源を守るための滋賀県の努力と、それに対する京都市の感謝の念。感謝金は、両自治体の良好な関係性を築き、未来へと繋ぐ大切な役割を担っていると言えるでしょう。
節水への意識と未来への展望
京都市では、節水機器の普及などにより、水道使用量はピーク時の1990年度と比べて約25%減少しています。 人口減少も進む中、感謝金の将来的な在り方については議論の余地があるかもしれません。 しかし、琵琶湖の水が京都市にとってかけがえのないものであることは、今後も変わりません。 感謝の気持ちを持ち続け、未来世代のために貴重な水資源を守っていくことが、私たちに課せられた重要な使命と言えるでしょう。