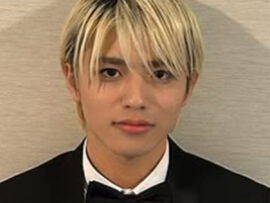皇室に関する話題は、常に国民の関心を集めています。小室眞子さん夫妻の米国での生活、悠仁親王の大学受験、愛子内親王、佳子内親王の結婚など、皇室メンバー一人ひとりの動向が注目を集め、メディアを賑わせています。
 皇室一般参賀
皇室一般参賀
明治時代から続く皇室報道は、時代と共にその様相を変えてきました。「権威」を重視した時代から、現代の「消費」的な報道まで、その変遷と課題について、名古屋大学大学院人文学研究科准教授の河西秀哉氏に話を伺いました。
皇室報道の変遷:昭和と平成の大きな変化
河西氏によると、昭和時代の皇室記者は長年その職に就いているベテランが多く、皇族との深い関係性を築いていました。当時の皇太子ご夫妻(現上皇ご夫妻)は非公開の記者会見を頻繁に開催し、記者たちは厳しい質問を投げかけていました。時には「今の回答はおかしいのではないか」「皇太子はこうあるべきではないか」といった提言めいた意見も飛び交い、皇族はそれらに即座に答える必要がありました。こうした記者との真剣なやり取りを通して、皇族の自己表現力は磨かれていったと考えられます。
小室眞子さん夫妻
しかし、平成時代に入ると、皇室記者の担当はローテーション制となり、経験の浅い記者が増えました。そのため、宮内庁や皇室の立場を深く考えさせるような難しい質問は減り、無難な質問が多くなりました。一方で、週刊誌やテレビのワイドショーは、よりセンセーショナルで消費的な皇室報道を展開するようになりました。雑誌の売上や視聴率を重視するあまり、報道の内容は過激化していったのです。
メディアの変化と皇室への影響
平成時代は、皇室が国民に身近な存在になった時代とも言えます。これは、ニュース番組よりもワイドショー、新聞よりも週刊誌が皇室報道の主要媒体となったことが大きな要因です。ワイドショーや週刊誌は、時に下世話な内容の報道を行い、それが一般大衆の関心を集めるようになりました。その結果、報道の内容はエスカレートし、バッシングとも取れるような報道も増えました。
では、皇族はこのようなメディアの報道についてどう思っているのでしょうか。河西氏は、あくまでも推測としながらも、ある程度は許容しているのではないかと考えています。
今後の皇室報道のあるべき姿とは
皇室報道の歴史を振り返ると、時代と共にメディアの役割や報道の在り方が変化してきたことが分かります。現代社会において、メディアは皇室と国民を繋ぐ重要な役割を担っています。皇室報道の未来を考える上で、メディアは「権威」と「消費」のバランスをどのように保ち、正確で公正な報道を続けていくのか、その責任は重大です。国民もまた、メディアリテラシーを高め、情報を受け取る側の責任を自覚する必要があると言えるでしょう。