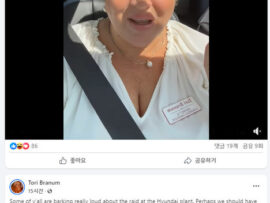2025年、イランの公共の場では、女性のヘジャブ(頭髪を隠すスカーフ)着用義務が引き続き厳しく徹底されています。この国を訪れ、市井の人々を取材する作家・金井真紀氏は、テヘランの街中で「風紀警察」に遭遇したと語ります。スカーフ着用に抵抗する女性たちが彼らに注意される場面も目の当たりにし、その存在と社会への影響について深く考察しました。この報告は、イランにおける女性の自由と法規制の現状を、生の声を通じて伝えるものです。
テヘラン繁華街での「風紀警察」との遭遇
イランの領土内では、外国人も含め、9歳以上のすべての女性が公共の場所でヘジャブと呼ばれるスカーフと、体の線を隠すためのコートの着用が法律で義務付けられています。日本の外務省の渡航情報にもこの点が明記されており、イランを訪れる際には常に意識しなければならない重要な規則です。
金井氏がテヘランの中心部、地下鉄タジュリーシュ駅周辺を訪れた際のことです。このエリアは伝統的なバザール、青果市場、ショッピングモール、モスクなどが密集し、平日午後でも人、車、バイク、リヤカーが入り乱れる活気に満ちた場所です。金井氏は通訳のメフディーさん(男性)とザフラーさん(女性)と共に、その混沌とした通りを歩いていました。
ザフラーさんが最初に異変に気づきました。「あ、あそこに警察がいます」。彼女の視線の先には、地下鉄の入り口付近に白いワンボックスカーが停まっており、その脇の歩道にはモスグリーンの制服制帽の男性警官が二人、そして黒いチャドルをまとった女性警官が一人立っていました。まさしく、噂に聞いていた「風紀警察」でした。
風紀警察は、女性が髪を出していないか、未婚の男女が一緒に歩いていないかなど、市民の道徳的行動を監視するために2006年に設立された機関です。彼らの任務は、「風紀を乱している」と見なした人々をその場で注意したり、時にはワンボックスカーに連行して署に勾留したりすること。違反者の多くはすぐに釈放されるものの、逮捕、勾留、鞭打ちといった厳しい処罰が下されるケースも存在します。2022年秋、地方からテヘランを訪れていたマフサー・アミーニーさんが警察署に連行された後に亡くなった事件も、この風紀警察によるものでした。この悲劇をきっかけに大規模な抗議運動が巻き起こり、「風紀警察の廃止」が報じられましたが、テヘランでの金井氏の目撃は、その存在が今なお健在であることを示唆しています。
 イランのテヘランでヘジャブ着用を監視する「風紀警察」と市民の様子を描いた金井真紀氏のイラスト
イランのテヘランでヘジャブ着用を監視する「風紀警察」と市民の様子を描いた金井真紀氏のイラスト
撮影断念と予期せぬ展開
風紀警察の3人組は金井氏たちから50メートル以上離れた場所に立っており、周囲には多くの人々が行き交っていました。この距離なら気づかれずに写真を撮れるかもしれない、と金井氏はポケットの中のスマートフォンを握りしめ、ザフラーさんに小声で尋ねました。「あの人たちを写真に撮ってもいいですかね?」。
ザフラーさんもまた声をひそめ、「危ないですよ」と忠告しました。彼らとは目を合わせずに通り過ぎるのが賢明である、というのが現地の常識のようです。金井氏は、一枚の写真のために不必要なトラブルに巻き込まれることを避け、撮影を諦めることにしました。自身の髪がスカーフからはみ出していないことを確認し、さりげなく歩を進めようとしたその時、予期せぬ出来事が起こりました。
なんと、通訳のメフディーさんが風紀警察の方へすいすいと近づいていくではありませんか。「あれ! ちょっとメフディーさん……」。金井氏の驚きをよそに、メフディーさんは女性警官の前に立ち、満面の笑みで「サラーム(こんにちは)」と話しかけたのです。この思いがけない行動は、緊張感に包まれたその場の空気を一変させ、イラン社会の複雑な一面を垣間見せる瞬間となりました。
結論
金井真紀氏のテヘランでの体験は、2025年の現在においてもイランにおける「風紀警察」の存在と、女性のヘジャブ着用義務が依然として厳しく運用されている現実を浮き彫りにしました。マフサー・アミーニーさんの死をきっかけとした大規模な抗議運動や「廃止」の報道にもかかわらず、その活動は続いており、市民生活の中に深く根付いていることが分かります。一方で、現場での予期せぬ人々の対応は、表面的な法律や報道だけでは見えない、より複雑で多面的なイラン社会の姿を示唆しています。この報告は、遠い国で繰り広げられる日常の中の抑圧と、それに対する多様な反応をリアルに伝える貴重な記録と言えるでしょう。
参考資料
- 金井真紀『テヘランのすてきな女』(晶文社)
- Yahoo!ニュース: 「風紀警察の注意をガン無視して通り過ぎる女性たち」 – Source link