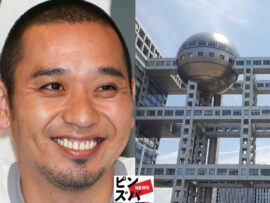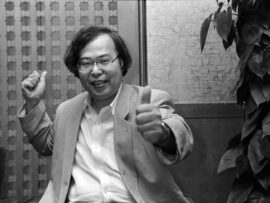沖縄県名護市辺野古の米軍基地移設工事現場付近で起きた死亡事故を巡り、県の対応に批判が集まっている。本記事では、事故の背景、県の見解、そして議会での議論について詳しく解説します。
事故の概要と県の初期対応
2023年6月、辺野古移設工事への抗議活動中に、警備員がダンプカーに巻き込まれ死亡する事故が発生しました。事故現場では、以前から事業者側が抗議者保護のためのガードレール設置を県に要請していたにもかかわらず、県はこれを拒否していました。
 沖縄県議会の様子
沖縄県議会の様子
県は事故後も「歩道である以上、歩行者の自由な通行を妨げる施設の設置はできない」という立場を崩さず、ガードレール設置要請を拒否し続けました。この対応には、地元住民や議会からも批判の声が上がりました。
県議会での追及と玉城知事の見解
2月25日の県議会本会議では、自民党の島袋大議員が玉城デニー知事に対し、事故への県の対応について厳しく追及しました。島袋議員は、県の消極的な姿勢を批判し、「知事も副知事も事故映像を見もしない。何ら対策を取ろうとしない」と指摘。さらに、「基地反対なら反対でいいが、こうした迷惑行為をさせないためにも、最善の策を取るのが県の仕事」と述べ、県の責任を問いました。
これに対し、玉城知事は「道路管理者としては、管理者本人が責任を有すると認識している」と述べるにとどまり、具体的な対策については明言を避けました。
ガードレール設置拒否の理由と批判
県はガードレール設置を拒否する理由として、「歩行者の自由な通行を妨げる」ことを挙げています。しかし、事故現場では抗議活動による交通渋滞や危険な状況が発生しており、安全対策の必要性が指摘されていました。
事故後、県はガードレールではなくラバーポールを設置しましたが、沖縄防衛局は「ラバーポールでは妨害行為を防止できず、事故の状況や背景を無視したものだ」と反発。県の対応の不十分さを批判しています。
事故後の対策と今後の課題
事故後、県はラバーポールを設置するなどの対策を取りましたが、根本的な解決には至っていません。抗議活動と工事の安全確保を両立させるためには、県、事業者、そして抗議活動を行う団体間の更なる協議と協力が不可欠です。
専門家であるA大学交通政策研究センターの佐藤教授は、「安全確保を最優先事項として、関係者間で真摯な対話を行うべきだ」と指摘しています。また、B市市民団体代表の田中氏は、「県は住民の声に耳を傾け、より効果的な安全対策を講じる必要がある」と訴えています。
まとめ
辺野古移設工事現場付近で起きた死亡事故は、抗議活動と工事の安全確保という難しい課題を改めて浮き彫りにしました。県は批判を受けながらも、ガードレール設置には消極的な姿勢を崩していません。今後、どのように安全対策を進めていくのか、県の対応が注目されます。