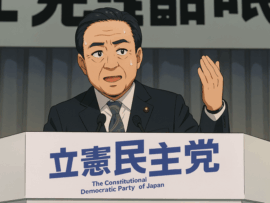NHK大河ドラマ「べらぼう」で描かれる江戸の異変。轟音や地面の揺れ、そして降り注ぐ灰…これらは天明3年(1783年)に発生した浅間山の大噴火によるものでした。この未曾有の災害は、江戸のみならず日本全国に甚大な影響をもたらし、やがて「天明の米騒動」という歴史的な社会不安へと繋がります。噴火はどのようにして米騒動を引き起こしたのか、その知られざる実態に迫ります。
浅間山、未曾有の噴火の猛威
天明3年(1783年)7月、上野国と信濃国の境にある浅間山(標高2568メートル)で大規模な噴火が発生しました。4月9日に始まった活動は6月下旬から頻度を増し、7月5日には激化。7月7日から翌朝にかけてプリニー式噴火が最盛期を迎え、その総噴出量は東京ドーム約403個分(0.5立方キロメートル)にも達したとされます。爆発音は遠く四国まで響き渡るほどでした。
 火山噴火や火山灰をイメージした写真
火山噴火や火山灰をイメージした写真
特に深刻だったのは、北麓の鎌原村を襲った土石雪崩です。村全体152戸が一瞬にして飲み込まれ、483名が犠牲となりました。また、焼けた石の落下による火災や、軽石による家屋の倒壊なども相次ぎました。発生した土石流は吾妻川、そして利根川を下り、遠く江戸湾や太平洋にまで到達したのです。
噴煙は成層圏に達し、上空約10キロメートル以上にまで到達。偏西風に乗って広い範囲に火山灰を降らせ、特に風下地域では激しい降灰に見舞われました。

噴火がもたらした飢饉と米価高騰
浅間山噴火の影響は、直接的な被害に留まりませんでした。広範囲に降り積もった火山灰は、農作物の生育に壊滅的な打撃を与えたのです。特に東北地方を中心に、日照不足や冷害も重なり、米は大凶作に見舞われました。
これにより、全国的に米の供給が激減。たちまち米価は記録的な高騰を始めました。さらに、この状況に目をつけた一部の商人が米を買い占め、売り惜しみを行ったため、市場に出回る米はさらに少なくなり、価格は一層跳ね上がりました。
生活の基盤である米が手に入らなくなった庶民は、食べるものに事欠く極度の困窮状態に追い込まれました。飢えに苦しむ人々が続出したのです。
頻発する暴動と「天明の米騒動」の実態
米価の高騰と深刻な食糧不足は、社会不安を爆発させました。天明3年から翌年にかけて、飢餓と困窮に耐えかねた人々は、米を買い占めた商人や富裕層に対して「米騒動」や「打ちこわし」といった形で抗議行動を起こしました。これらの騒動は江戸を含む全国各地で頻発し、社会秩序は大きく乱れました。
幕府は米の価格統制や買い占めの禁止令、備蓄米の放出といった対策を講じましたが、未曾有の大凶作とそれに乗じた不正行為の前には十分な効果を得られませんでした。
食糧不足は解消されず、飢餓や栄養失調による病気が蔓延し、全国各地で多数の死者が出ました。浅間山の噴火をきっかけとした天明の飢饉とそれに伴う米騒動は、江戸時代後期における最も悲惨な出来事の一つとして歴史に刻まれています。
結論
浅間山天明の大噴火は、単なる自然災害に終わらず、その後の大規模な飢饉と米価高騰を引き起こし、社会全体を揺るがす「天明の米騒動」へと発展しました。この歴史的な出来事は、自然の猛威が経済、社会、そして人々の生活にいかに深刻な影響を与えるかを示す一例であり、後世に多くの教訓を残しています。
参考資料:
https://news.yahoo.co.jp/articles/32918fde93b5dd48611a99582fb1a72c1ccfa28f