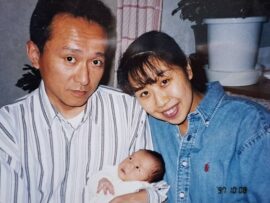広島地裁福山支部で11日、小学校教諭が児童への指導中に羽交い締めにした行為が暴行罪にあたるかどうかが争われた刑事裁判の判決が言い渡されます。学校教育法が教職員に認める「懲戒権」の範囲内だったのか、それとも法が禁じる「体罰」に逸脱したのかが最大の争点となっており、教育現場における指導のあり方について大きな議論を呼んでいます。
事件の概要と経緯
この裁判は、広島県福山市立の小学校に勤務する男性教諭(37歳)が昨年5月10日、当時小学6年生だった男子児童(11歳)に対し、後ろから羽交い締めにする暴行を加えたとして起訴されたものです。
事件後、福山市教育委員会は学校側の調査結果などを踏まえ、教諭の行為は「体罰には該当しない」との判断を示しました。しかし、男児の保護者が警察に被害届を提出したことを受け、刑事事件として捜査が進められました。
教諭はその後、略式起訴され、昨年12月に福山簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受けました。教諭はこの命令を不服として正式裁判を申し立て、今回の公判に至りました。
 広島県福山市役所の外観。教諭が勤務する小学校の所在地。
広島県福山市役所の外観。教諭が勤務する小学校の所在地。
公判での主な争点と主張
公判では、教諭が男児を注意しようと腕をつかんで押さえつけた後、男児が暴れたため羽交い締めにしたとされる一連の行為が、学校教育法が認める教員の懲戒権の範囲内だったのか、あるいは正当防衛にあたるのかが主な争点となりました。
検察側は、男児が痛みを感じていたことや、教諭との間に大きな体格差があった点を指摘。「羽交い締めは過度な有形力の行使であり、懲戒権の範囲を明らかに逸脱している」と主張しました。さらに、「被害者への積極的な加害意思が認められる」として、正当防衛の成立も否定。教諭に対し罰金20万円を求刑しました。
これに対し弁護側は、教諭の行為は「暴れる男児を落ち着かせ、適切に指導するための正当な行為であり、懲戒権の範囲内で行われた」と反論しました。「暴れる児童から自身の身を守る必要もあった」として、正当防衛にもあたると主張し、無罪を求めました。弁護側はまた、「このような行為が暴行と見なされるならば、教育現場での指導が萎縮し、教員が児童生徒に踏み込めなくなる」と訴え、判決が教育現場に与える影響の大きさを強調しました。
「暴行罪」とは
刑法に定められる「暴行罪」は、他人の身体に対し不法な有形力を行使した場合に成立する犯罪です。ここでいう有形力とは、殴る、蹴るといった直接的な物理力だけでなく、相手の身体に触れる、物を投げつけるなど、物理的な影響を及ぼすすべての行為を含みます。ただし、暴行の結果、相手が怪我を負った場合は、「傷害罪」となり、より重い罪となります。暴行罪の法定刑は「2年以下の拘禁刑」、「30万円以下の罰金」、「拘留」、「科料」のいずれかと規定されています。今回の裁判では、児童に怪我はなかったため、暴行罪として問われています。
判決の行方と教育現場への影響
この裁判は、学校教育の現場で日々行われる指導行為が、どこから体罰となり、どこまでが許容される「懲戒」の範囲なのか、という長年の難しい問題に司法が判断を示すものです。教員が児童生徒の安全確保や秩序維持のために実力を行使することが、どのような場合に正当とされ、どのような場合に違法となるのか。福山地裁福山支部が11日に下す判決は、同様の事案における今後の判断基準や、全国の教育現場での指導のあり方に大きな影響を与える可能性があります。判決の内容が注目されます。
出典: 読売新聞