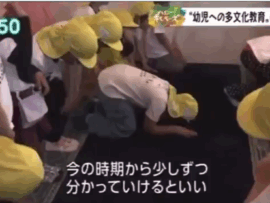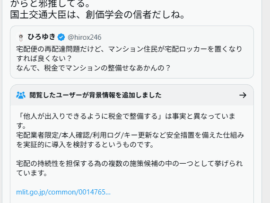2023年、秋田県ではツキノワグマによる人身事故が急増し、大きな社会問題となりました。ブナ、ミズナラ、コナラといったクマの主要な食料となる木の実が凶作だったことが背景に挙げられ、「冬眠できないクマが凶暴化しているのでは?」と不安の声も聞かれました。しかし、実際のところはどうだったのでしょうか?自然写真家である永幡嘉之氏の著書『クマはなぜ人里に出てきたのか』(旬報社)を参考に、その真相に迫ります。
クマの人里への出没:餌不足だけが原因?
 クマの餌となるドングリ
クマの餌となるドングリ
クマが人里に現れる原因として、まず考えられるのは餌不足です。2023年は特にドングリが凶作だったため、クマが食料を求めて人里に降りてきたのは事実でしょう。しかし、それだけでしょうか?実は、クマの出没には地形的な要因も大きく関わっているのです。
出没しやすい地形とは?
山形県でのクマの出没状況を長年観察してきた永幡氏は、クマが住宅地に現れる場所にはある共通点があることに気づきました。それは、水田の中に川に沿って樹林があり、特に河岸段丘や広い河川敷がある場所です。クマは夜間に川沿いの森を伝って下りてきて餌を探し、夜明けまで食べ続けます。そして、夜が明けて人々が活動を始めると、森に戻れずにパニックになり、学校や人家に逃げ込んだり、住宅地を走り抜けたりするのです。ツキノワグマの遺伝子研究の専門家であり、猟友会にも所属する行政職員の鵜野氏も、この見解に同意しています。
事故はなぜ早朝に集中するのか?
人身事故の多くは早朝に発生しています。これは、クマが夜間に餌を求めて人里に下りてきて、夜明けとともに人々の活動が始まり、遭遇してしまうことが原因です。また、茂みに隠れて人が通り過ぎるのを待っている際に人が近づいてしまったり、子連れの母グマが子グマを守ろうとして襲いかかったりするケースもあります。これらの事故は、いずれもツキノワグマの通常の行動から説明できるものです。
クマは人に慣れるのか?凶暴化するのか?
2023年の秋田県での人身事故は例年の10倍以上にものぼりましたが、これはクマの密度が高まったことによる必然的な結果と言えます。事故の報道が増えると、どうしても恐怖をあおるような風潮が生まれてしまいますが、2016年に秋田県鹿角市で発生したような、クマが人間を襲う事件とは異なる性質のものだと考えられます。重要なのは、クマは人に危害を加えないことを学習するということです。しかし、狩猟が解禁されると状況が一変します。
狩猟の影響
狩猟によってクマが警戒心を強め、人間を避けるようになるという側面がある一方で、人間に対する恐怖心が薄れ、結果的に人里への出没につながる可能性も指摘されています。 例えば、著名なクマ研究者である山田博士(仮名)は、「狩猟によるクマの行動への影響は複雑で、更なる研究が必要」と述べています。 クマの行動を理解し、適切な対策を講じるためには、狩猟の影響についても慎重に検討する必要があります。
クマとの共存に向けて
クマとの共存は容易ではありませんが、クマの生態を理解し、適切な対策を講じることで、被害を最小限に抑えることが可能です。 恐怖心を煽るのではなく、冷静に現状を分析し、共存への道を探ることが重要です。 そのためには、行政、専門家、そして地域住民が一体となって取り組む必要があります。