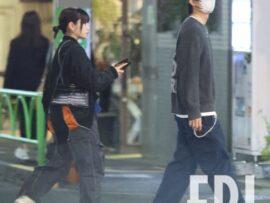第二次世界大戦末期、日本海軍最後の名戦闘機として知られる「紫電改」。その一機が、鹿児島県沖の海底に80年間もの間、静かに眠り続けている。今秋、地元の市民団体が引き揚げに挑戦しようとしているこの機体には、米軍機との死闘の末、力尽きた悲劇の歴史が刻まれている。今回は、戦争遺産として後世に語り継ぐべく立ち上がった人々の活動と、海底に眠る「紫電改」の物語に迫る。
300m先の海底に眠る「剣部隊」隊長機:引き揚げへの挑戦
海底調査で見つかった「紫電改」の現状
鹿児島県阿久根市の折口海岸。エメラルドグリーンの海面を指さしながら、「沈んでいるのはここから約300メートル先。想定よりも状態は良くない」と語るのは、「紫電改・林大尉機を引き揚げる会」会長の肥本英輔さん(70)だ。
 海底に沈む紫電改を指す肥本英輔さん
海底に沈む紫電改を指す肥本英輔さん
昨年の潜水調査で水深3メートルの海底から発見された機体は、「剣部隊」の異名で知られた第343海軍航空隊・戦闘第407飛行隊の隊長、林喜重大尉(戦死後、少佐に昇進)が搭乗していたものだ。林大尉を知る人も少なくなっていく中、「10年早く気づいていれば…」と悔やむ肥本さんは、「何とか今年中に引き揚げたい」と強い決意を語る。
林大尉の最期:目撃者の証言
1945年4月21日早朝、米軍のB29爆撃機を迎撃するため、林大尉は現在の霧島市にあった第一国分基地から「紫電改」で出撃した。出水市上空で1機の撃墜を報告した後、沖合に不時着水したという。
 林喜重大尉
林喜重大尉
当時、いちき串木野市に住んでいた早川浩一郎さん(89)は、海面に漂う「紫電改」を目撃した。地元住民によって助け出された林大尉は、すでに息絶えていたという。早川さんの勉強部屋として使われていた近くの小屋に安置された林大尉の遺体について、早川さんは「顔には傷もなく、きれいだった。戦ってくれたことへの感謝と、亡くなったことへの悲しみが込み上げてきた」と当時を振り返る。米軍の攻撃が激しさを増す中、近くの集落は焼夷弾によって焼き払われた。早川さんは「子ども心に『この戦争は負ける』と思った。あんな戦争は二度と経験したくない」と静かに語った。
引き揚げへの想い:「紫電改」に込められた歴史の重み
引き揚げ活動の始まり
かつて出水市の歴史館で働いていた肥本さんは、愛機とともに散った林大尉の悲劇を知り、文献調査や地元住民への聞き取りを開始。ダイバーの友人の協力も得て、海底調査で機体の残骸を確認すると、「紫電改・林大尉機を引き揚げる会」を設立し、引き揚げのための寄付を募り始めた。
国内現存機はわずか1機
「紫電改」は、太平洋戦争末期に登場した高性能戦闘機であり、零戦の後継機として開発された。その優れた性能にもかかわらず、終戦までに生産された機体はわずか400機程度。現在、国内で完全な形で現存する「紫電改」は、愛知県豊山町の航空自衛隊小牧基地に展示されているわずか1機のみとなっている。航空史研究家の田中一郎氏(仮名)は、「紫電改は、当時の日本の航空技術の粋を集めた傑作機。この貴重な機体を引き揚げ、保存することは、戦争の歴史を伝える上で非常に重要な意義を持つ」と語る。海底から引き揚げられた「紫電改」は、修復・保存され、後世に戦争の悲惨さと平和の尊さを伝えるための貴重な資料となるだろう。
未来へのメッセージ:平和への願いを込めて
林大尉の「紫電改」の引き揚げは、単なる機体の回収ではなく、戦争の記憶を風化させないための重要な取り組みだ。引き揚げられた機体を通して、後世の人々が戦争の悲劇を学び、平和の尊さを改めて認識するきっかけとなることを願う。