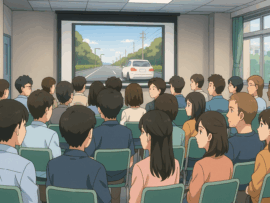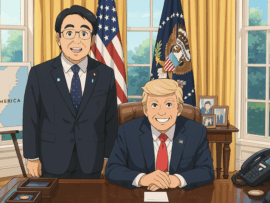高齢化社会が進む日本では、訪問介護の需要は年々増加しています。しかし、その一方で、訪問介護事業所の倒産が過去最多を更新するという深刻な事態も発生しています。この記事では、新潟県での訪問介護の現場の様子、倒産増加の背景、そして新潟県独自の支援策について詳しく解説します。
101歳の一人暮らしを支える訪問介護
新潟県村上市。11年のキャリアを持つベテランヘルパー、榎本麻奈美さん(32歳)が、101歳の須貝トシエさんの自宅を訪れました。30年前に夫を亡くし、現在は一人暮らしの須貝さん。立ち上がることもままならず、「要介護2」と認定されています。以前は姪が世話をしていたものの、高齢のため負担が大きくなり、3年前から週3回、榎本さんのような訪問介護ヘルパーのサポートを受けています。
 alt
alt
榎本さんは、洗濯物を干したり、冷蔵庫の食材で料理を作ったり、須貝さんの要望に合わせてきめ細やかなサポートを提供しています。「利用者さんが待っていてくださる事がやりがい」と語る榎本さん。しかし、こうした献身的なヘルパーを支える訪問介護事業所の経営は、厳しい現実と向き合っています。
訪問介護事業所の倒産件数、過去最多を更新…その背景とは?
東京商工リサーチの調査によると、2024年に倒産した介護事業者は172社と過去最多を記録。そのうち約半数を訪問介護事業所が占めています。要因の一つとして挙げられるのが、訪問介護の基本報酬の引き下げです。2025年2月、新潟県内の訪問介護事業者たちは、物価高騰に加えて報酬が引き下げられたことに対し、怒りの声を上げました。
新潟県民主医療機関連合会によると、都市部では訪問介護事業所の黒字率が高い傾向にあります。マンションなどの集合住宅が多い都市部では、短時間で多くの利用者宅を訪問できるためです。そのため、政府は訪問介護の基本報酬を引き下げたと考えられています。しかし、新潟県のように一軒家が多く、利用者宅間の移動距離が長い地域では、都市部ほど利益を上げにくいのが現状です。さらに、冬場の積雪により移動時間が長引くこともあり、十日町市や糸魚川市などでは、多くの事業所が赤字経営に陥っています。
県民医連が県内398の訪問介護事業所を対象に行ったアンケートでは、回答した139事業所の約8割が「事業継続が厳しくなる」または「悪化する」と回答しました。
新潟県の取り組みと今後の課題
こうした状況を受け、新潟県では独自の支援策を検討し始めています。例えば、移動距離に応じた報酬加算や、冬期の除雪費用補助などが検討されています。また、事業所間の連携強化やICTの活用による効率化なども推進していく方針です。

県民医連の宮野大事務局次長は、「今回のアンケート結果から、国の判断は誤りだったと確信している。訪問介護の基本報酬引き下げについては、次期改定を待たずに即時撤回が必要」と訴えています。介護報酬の見直しは3年に1度ですが、現場の声を真摯に受け止め、早急な対応が求められています。
訪問介護の未来を守るために
訪問介護は、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすために不可欠なサービスです。質の高いサービスを維持するためにも、事業所の経営安定化は喫緊の課題です。国、地方自治体、そして事業者が一体となって、持続可能な訪問介護システムを構築していく必要があります。