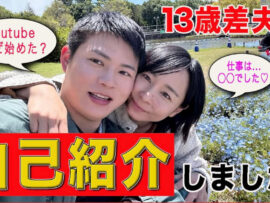花粉症の季節がやってきました。くしゃみ、鼻水、鼻づまり…、毎年悩まされる方も多いのではないでしょうか。今回は、増加する高齢者の花粉症に焦点を当て、最新の対策方法や注意点について詳しく解説します。
花粉症の現状:増加する高齢者と深刻な経済損失
スギやヒノキの花粉が猛威を振るう季節。もはや国民病とも言える花粉症ですが、近年、高齢者の患者数が増加していることはご存知でしょうか。2023年12月のユーグレナ社による調査では、60歳以上の花粉症患者のうち、約3割が60歳以降に発症したと報告されています。
花粉症による経済損失も深刻です。パナソニック社が発表したデータによると、花粉症による労働力低下の経済損失は1日あたり約2320億円にものぼります。第一生命経済研究所の試算では、花粉症悪化による外出自粛で消費が約5691億円減少したというデータも。花粉症対策は、個人の健康だけでなく、日本の経済にとっても重要な課題となっています。
 花粉症の人の様子
花粉症の人の様子
高齢者の花粉症:特有の症状と対策の難しさ
高齢者の花粉症は、若年者とは異なる特徴があります。くしゃみや鼻水よりも鼻づまりが強く、皮膚のバリア機能低下により、花粉が付着すると湿疹やかゆみなどの皮膚炎を起こしやすい傾向があります。顔や首などの露出部分に症状が現れやすく、掻きむしることで悪化し、QOL(生活の質)を著しく低下させます。
抗ヒスタミン剤のリスク:高齢者は要注意
花粉症治療の主軸となる抗ヒスタミン剤ですが、高齢者にとっては注意が必要です。眠気などの副作用は転倒リスクを高め、譫妄や排尿障害を引き起こす可能性も。近年では、認知症リスクとの関連性も指摘されています。2022年に台湾の研究チームが発表した研究では、65歳以上で抗ヒスタミン剤を使用すると認知症リスクが1.8倍増加すると報告されています。特に男性や併存疾患のある方はリスクが高いとされています。
高齢者に最適な花粉症対策とは?
では、高齢者はどのように花粉症対策を行えば良いのでしょうか?抗ヒスタミン剤の連用は避け、医師と相談しながら副作用の少ない薬を選ぶことが大切です。 「高齢者の花粉症治療においては、個々の状況を把握し、副作用のリスクを最小限に抑えることが重要です」と、アレルギー専門医の佐藤先生(仮名)は述べています。 点鼻薬や点眼薬なども有効な選択肢となります。
日常生活での対策:花粉を寄せ付けない工夫
日常生活では、花粉を体内に取り込まない工夫が重要です。外出時はマスクやメガネを着用し、帰宅後は衣類についた花粉をよく払い落としましょう。室内では空気清浄機を使用し、こまめな換気を心掛けましょう。
花粉症を乗り越えて快適な春を
花粉症は適切な対策を行うことで症状を軽減できます。高齢者の方は特に、薬の副作用に注意しながら、医師と相談して治療方針を決めることが重要です。日常生活での工夫も併せて、つらい花粉シーズンを乗り越え、快適な春を過ごしましょう。