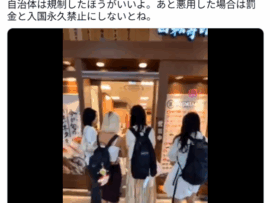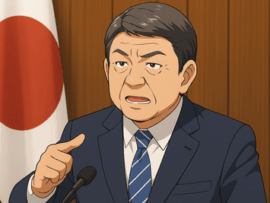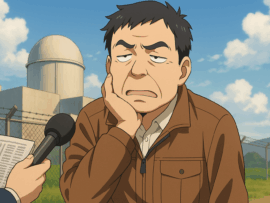日本の温泉、その魅力的な湯けむりに癒やしを求める人々にとって、今、深刻な問題が突きつけられています。それは、温泉水の枯渇です。かつては豊富に湧き出ていた温泉が、今まさに枯渇の危機に瀕しているのです。一体何が起きているのでしょうか?この記事では、日本の温泉を取り巻く現状と、その背景にある様々な要因について深く掘り下げていきます。
温泉枯渇の現状
近年、日本の主要温泉地では、温泉水の枯渇が深刻化しています。佐賀県の嬉野温泉では、2020年には平均50メートルだった水深が、2023年には39.6メートルまで低下。わずか4年間で20%も減少しているのです。北海道のニセコ温泉でも、2021年以降、水深が15メートルも低下したという報告があります。
 alt
alt
これらの深刻な状況を受け、地方自治体では日帰り入浴の禁止措置を拡大。一部地域では、深夜営業を中止したり、シーズン中には宿泊客以外の日帰り入浴を禁止するなどの対策が取られています。
温泉枯渇の要因
温泉枯渇の背景には、様々な要因が複雑に絡み合っています。まず挙げられるのが、オーバーツーリズムです。コロナ禍が落ち着き、円安も相まって、日本への外国人観光客が急増。2024年には過去最高の3680万人を記録しました。観光客の増加は、温泉水の使用量を押し上げる大きな要因となっています。
一人温泉の増加
そして、もう一つの大きな要因が「一人温泉」の急増です。西洋の観光客は、大衆浴場で他人と一緒に入浴する日本の文化に抵抗があるため、一人温泉を好む傾向があります。ホテル側も、高価格帯の一人温泉付き客室を増やすことで収益を上げようとするため、結果的に温泉水の消費量が増加しているのです。温泉旅館経営コンサルタントの山田氏(仮名)は、「一人温泉の需要増加は、温泉資源の持続可能性という観点から、大きな課題となっている」と指摘しています。
インフラ老朽化の問題
さらに、老朽化した配管などのインフラ問題も温泉枯渇に拍車をかけています。中央温泉研究所の大塚晃弘研究員は、「多くの温泉地では適切な管理が行われておらず、温泉水が無駄に消費されている」と指摘。インフラ整備の必要性を訴えています。
政府の対策
こうした状況を受け、日本政府はオーバーツーリズム対策として、入国税の引き上げや宿泊税の新設などを検討しています。しかし、これらの対策だけで温泉枯渇問題を根本的に解決できるのか、疑問の声も上がっています。
今後の展望
日本の温泉は、単なる観光資源ではなく、日本の文化や歴史と深く結びついた貴重な財産です。温泉を守っていくためには、観光客、事業者、そして行政が一体となって、持続可能な温泉利用に取り組む必要があります。例えば、温泉水の再利用技術の導入や、節水意識の啓発活動などが考えられます。「温泉ソムリエ」として知られる田中氏(仮名)は、「温泉の未来を守るためには、一人ひとりが温泉の価値を理解し、大切に利用していくことが重要だ」と強調しています。
温泉の未来を守るために、私たち一人ひとりができることは何か?今こそ、真剣に考えて行動に移す時です。