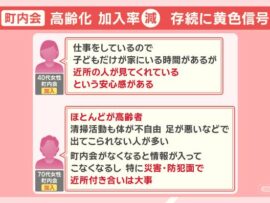財務省への抗議デモが全国的に広がりを見せています。生活苦にあえぐ国民の不満が爆発し、まるで江戸時代の百姓一揆を彷彿とさせるこの状況。一体何が起きているのでしょうか?この記事では、デモの背景や専門家の意見、そして今後の展望について詳しく解説します。
財務省解体デモ急増の背景
コロナ禍、ウクライナ戦争、そして物価高騰…生活を取り巻く環境は厳しさを増すばかりです。こうした状況下で、政府は増税路線を継続。国民の不満は日に日に高まり、その矛先は財政政策を担う財務省へと向けられています。インターネット上では、「デモは無意味」「財務省のせいではない」といった批判的な声も上がっていますが、本当にそうでしょうか?
 alt財務省前で抗議の声をあげるデモ参加者たち。生活苦への不満が募っている様子が伺えます。(写真:編集部・野村昌二)
alt財務省前で抗議の声をあげるデモ参加者たち。生活苦への不満が募っている様子が伺えます。(写真:編集部・野村昌二)
京都大学大学院の藤井聡教授(元内閣官房参与)は、「財務省へのデモは起こるべくして起きた」と指摘します。1997年の消費税増税以降、日本経済は低迷。コロナ禍やウクライナ戦争の影響も相まって、国民の貧困化は深刻さを増しています。生活苦にあえぐ国民の声に、政府は十分な対策を講じてきたと言えるでしょうか?
江戸時代の百姓一揆との類似点
藤井教授は、現在のデモを江戸時代の百姓一揆と比較します。飢饉などで幕府の収入が減ると、幕府は年貢の割合を増やし、農民の負担を増大させました。生活苦に耐えかねた農民は、一揆を起こして抗議したのです。現在のデモは暴力的な行為ではありませんが、生活苦に追い込まれた国民が声を上げる構図は、百姓一揆と酷似していると言えるでしょう。
日本の税金・社会保障の国民負担率は、1975年度の25.7%から2025年度には46.2%(見通し)にまで上昇。約半世紀で2倍近くになっています。この急激な負担増は、国民生活に大きな影響を与えていることは間違いありません。
なぜ財務省が標的に?
国民の怒りの矛先は、本来であれば政府に向けられるべきです。しかし、現在はその矛先が財務省に向けられています。その背景には、国民の政治不信があると藤井教授は指摘します。岸田政権や石破政権の経済政策の背後には、財務省の意向が強く働いているのではないか?国民はそう疑っているのです。
財務省は、歳入(税金)と歳出(予算)という巨大な権限を握っています。増減税によって歳入を調整し、特定予算を調整することで歳出もコントロールできる。財務省は、この「アメとムチ」を駆使して、政治家、財界、さらにはマスメディアまでも支配しているのではないか、という疑念が国民の間で広がっているのです。
財務省の責任と改革の必要性
財務省は、経済成長の義務を負っていません。彼らの責務は、財政の健全化のみ。そのため、財政均衡を大義名分に増税と予算カットを進めてきました。藤井教授は、財務省がこの姿勢を改めなければ、「財務省解体」の声はさらに高まると警告します。
財務省改革の具体策
海外では、米国や英国のように徴税権と予算編成権を持つ組織を分けている国もあります。また、イタリアやフランスのように、日本と同様に一つの官庁が担当している国もありますが、これらの国では「経済成長」を義務付けています。日本でも、財務省に経済成長の責任を負わせるべきだという意見が出ています。しかし、明治維新以来、この体制は変わっていません。財務省のマインドを変えるのは容易ではないでしょう。
藤井教授は、財務省から主税局と国税庁を分離し、財務省の権限を弱体化させるべきだと提言しています。この改革によって、財政政策と経済成長のバランスがとれるようになる可能性があります。
今後の展望
財務省への批判は、将来への不安を抱える人々の切実な声です。政治はこの声に耳を傾け、真摯に対応していく必要があります。財務省の改革、そして国民生活の向上に向けた具体的な政策の実現が、今後の日本にとって不可欠です。