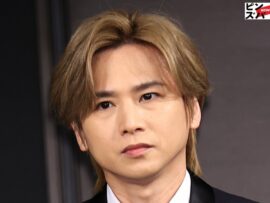高齢化社会が進む日本において、訃報に触れる機会も増えています。そんな中、近年よく目にする「老衰」という死因。著名人の訃報でも頻繁に見かけるようになりましたが、どこか違和感を感じている方も少なくないのではないでしょうか。今回は、この「老衰」という言葉に焦点を当て、日本人の死生観との関わりについて深く掘り下げていきます。
老衰とは何か? 医学的見地と社会通念のズレ
「老衰」と聞くと、穏やかな最期を迎えた印象を持つかもしれません。しかし、医学的にはどうなのでしょうか? 厚生労働省の統計(2022年人口動態統計)によると、死因の第3位に老衰がランクインしています。これは医療技術の進歩により、これまで特定の病名で診断されていたケースが、寿命を迎える自然な流れとして「老衰」と判断されるようになったことも一因と考えられます。
 老人の穏やかな表情
老人の穏やかな表情
一方で、作家の下重暁子氏は著書『怖い日本語』(ワニブックス【PLUS】新書)の中で、「老衰」という言葉への違和感を表明しています。著名人の訃報で「老衰」とされることに疑問を呈し、生前の功績を考えると、単なる「老衰」で片付けてしまって良いのかという問題提起をしています。
例えば、瀬戸内寂聴さん、篠山紀信さん、鈴木健二さん、山田太一さん、富岡多恵子さん、大江健三郎さん、永井路子さん、森英恵さんなど、多くの著名人が「老衰」で亡くなったと報道されています。もちろんご高齢ではありましたが、具体的な病名を伏せて「老衰」とすることに、違和感を感じる方もいるでしょう。
死因における「老衰」の増加と背景
「老衰」が死因の第3位になったのは2018年。それ以前は「脳血管疾患」が3位でしたが、医療の進歩により、より詳細な診断が可能になったことで、「老衰」とされるケースが増加したと考えられます。 高齢化社会の進展とともに、この傾向は今後も続くことが予想されます。
言葉の選び方がもたらす影響
「老衰」に限らず、言葉の選び方は私たちの認識に大きな影響を与えます。「心不全」や「呼吸不全」も、厳密には病名ではなく、死に至る最終的な状態を表す言葉です。 これらの言葉は、具体的な病名よりも穏やかな印象を与える可能性がありますが、同時に情報が不足しているとも言えます。
訃報における情報公開と遺族の想い
訃報における死因の公表は、遺族の意向が尊重されます。具体的な病名を公表したくない場合や、故人のプライバシー保護の観点から、「老衰」などの表現が選ばれることもあるでしょう。 しかし、情報公開とプライバシー保護のバランスは、常に難しい問題です。
日本人の死生観との関わり
「老衰」という言葉への違和感の背景には、日本人の死生観が影響していると考えられます。長寿を尊ぶ文化がある一方で、死をタブー視する傾向も根強く残っています。 そのため、直接的な死因に触れることを避け、「老衰」という曖昧な表現で覆い隠そうとする意識が働くのかもしれません。
今後の死生観の変化と向き合い方
高齢化社会の進展とともに、死はより身近な存在になりつつあります。 「老衰」という言葉への違和感を通して、死に対する考え方や向き合い方を改めて見つめ直す必要があるのではないでしょうか。 大切なのは、故人の人生を尊重し、その死を悼む気持ちを持つことです。言葉の表面的な意味にとらわれず、その背後にある想いを汲み取ることが重要です。