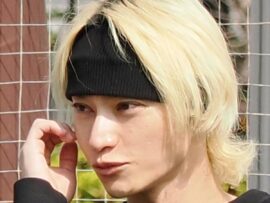プレゼンテーションやスピーチ、人前で話す機会は誰にでもあるものです。緊張で頭が真っ白になったり、伝えたいことがうまく伝わらなかったり…そんな経験はありませんか?この記事では、現役東大生であり、高校卒業時の名スピーチで話題となった土田淳真氏の経験に基づき、人前で話す際に役立つ「アドリブ力」の重要性と鍛え方について解説します。
原稿に頼らない、自由なスピーチ
土田氏は、式典などの公式な場を除き、原稿を用意しないことを心掛けているといいます。その理由は大きく分けて2つ。1つ目は、原稿があると話し手と聞き手の間に壁が生じ、コミュニケーションが阻害されるため。2つ目は、原稿に縛られることで、その場の雰囲気や聞き手の反応に合わせた柔軟な対応ができなくなるためです。
 alt:壇上でスピーチをする男性
alt:壇上でスピーチをする男性
著名なコミュニケーションコーチである田中一郎氏も、「原稿に頼りすぎると、聞き手との心のつながりが薄れてしまう」と指摘しています。スピーチは一方的な情報伝達ではなく、聞き手との双方向のコミュニケーションであるべきです。
伝えたいことを多角的に捉える
土田氏は、話す内容の一字一句を暗記するのではなく、「伝えたいこと」を様々な角度から表現する方法を事前に考えておくことを重視しています。聞き手の反応や理解度に合わせて、複数のストーリーや例え話を用意することで、より効果的にメッセージを伝えることができるのです。
状況に合わせた柔軟な対応
例えば、聞き手が特定の話題に興味を示した場合、それに関連するエピソードを付け加えたり、逆に理解が難しそうな場合は、より分かりやすい表現で説明したりといった工夫が重要です。まるでジャズミュージシャンが即興演奏で観客を魅了するように、状況に合わせて柔軟に対応することで、聞き手の心に響くスピーチを実現できるのです。
アドリブ力を鍛えるための実践的な方法
では、どのようにすればアドリブ力を鍛えることができるのでしょうか?土田氏は、以下の3つのポイントを挙げています。
1. 複数の表現方法を準備する
同じ内容でも、様々な言い回しや例え話で表現できるように練習しましょう。例えば、「この商品は高品質です」と言う代わりに、「職人が一つ一つ丁寧に作り上げた、こだわりの逸品です」と表現することで、より具体的なイメージを伝えることができます。
2. 聞き手の反応を観察する
スピーチ中は、聞き手の表情や反応を常に観察し、理解度や興味に合わせて内容を調整しましょう。うなずきや笑顔が多い場合は、その話題を深掘りしたり、逆に退屈そうな場合は、テンポよく次の話題に移るなどの工夫が大切です。
3. 練習を積み重ねる
アドリブ力は一朝一夕で身につくものではありません。友人や家族の前で練習したり、スピーチの機会があれば積極的に挑戦することで、経験を積み重ねていきましょう。
まとめ:アドリブ力でスピーチをもっと魅力的に
「伝える力」は、現代社会において必須のスキルです。原稿に頼らず、聞き手との共感を大切にすることで、より効果的なコミュニケーションを実現できるはずです。今回ご紹介したポイントを参考に、あなたもアドリブ力を磨いて、自信を持って人前で話せるようになりましょう!