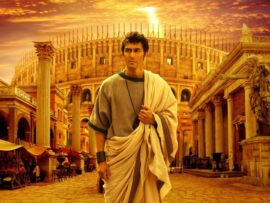タレントの辻希美さんと夫である杉浦太陽さん夫妻の間に誕生した第五子となる次女の名前が「夢空(ゆめあ)」と発表され、大きな話題を呼んでいます。辻さんは8月15日、自身のインスタグラムを通じて「家族みんなが納得する名前が良かったので家族で沢山話し合った」と、命名に至るまでの深い思いを報告しました。これに対し、夫の杉浦さんも「何度も何度も家族会議して、みんなで決めた名前」と、家族全員で熟考した結果であることを強調しています。SNSやニュース記事のコメント欄には、両親へのいたわりの言葉や新たな命の誕生を祝う温かいメッセージが多数寄せられる一方で、「読めない」「いわゆるキラキラネームだ」といった、子の名前に対する様々な反応が噴出しました。
 辻希美さんと杉浦太陽さんの夫妻、そして命名されたばかりの第五子・夢空(ゆめあ)ちゃんが写る家族写真。幸せそうな表情を見せている。
辻希美さんと杉浦太陽さんの夫妻、そして命名されたばかりの第五子・夢空(ゆめあ)ちゃんが写る家族写真。幸せそうな表情を見せている。
しかし、中には限度を超えたような心ないコメントも散見されます。もしこれらの発言が著しくひどいと判断された場合、法的に何らかの問題が生じる可能性はあるのでしょうか。インターネット上の誹謗中傷問題に詳しい弁護士の見解を求めました。
溢れる心ない声:「親の知性」「エゴ」といった批判
「キラキラネームを安易につける親は、子どもの将来を真剣に考えているとは言えない」。ニュース記事のコメント欄やSNS上では、辻さん夫妻の命名に対し、単なる批判的な意見に留まらず、過剰な攻撃と受け取れる投稿が複数見受けられます。具体的には、「子供の名前で親の知性がどれだけあるのかわかる。こんなDQNネームつける親にはなりたくないね」「感覚が完全にバグってるね」「やっぱり親のエゴが酷いな」といった、親の人格や判断力を一方的に貶めるような内容が含まれています。
これらの投稿が、辻さん、杉浦さんといった親に対する誹謗中傷、あるいは幼い夢空ちゃん本人に対する誹謗中傷として法的に捉えられる可能性はあるのでしょうか。この点について、インターネット問題の専門家である清水陽平弁護士に詳細を伺いました。
清水陽平弁護士が解説する名誉毀損と名誉感情侵害の境界線
清水陽平弁護士によると、「夢空ちゃん」の名前に関するSNSやインターネット上の投稿が、名誉毀損や名誉感情侵害(侮辱)に認定されるか否かは、その内容が社会的評価の低下を招くものであるか、あるいは社会通念上許される限度を超えているかによって判断されます。
名誉毀損が成立するのは、特定の事実を摘示することで個人の社会的評価を低下させる内容が発信された場合です。今回のケースで投稿されているコメントは、名前自体や親に対する意見や感想が大半を占めます。意見や感想であっても、それが社会的評価を損なう場合もありますが、多くは人格に対する攻撃的な内容に当たると考えられます。
清水弁護士は、この件については名誉毀損よりも「名誉感情侵害(侮辱)」の問題として捉える方が適切であると指摘します。名誉感情侵害とは、個人の名誉感情を不当に侵害する行為であり、社会通念上許される限度を超えていると評価できる場合に成立します。何をもって「社会通念上許される限度を超える」と判断するかは、投稿の内容、表現の度合い、繰り返し行われているかなど、様々な要素を総合的に考慮して決められます。特に、人格攻撃に至るような発言や、執拗な繰り返し投稿が行われるケースでは、限度を超えていると判断されやすくなります。
具体的に、指摘されているコメントの例を見てみましょう。「『子供の名前で親の知性がどれだけあるのかわかる』で始まる投稿は、親の知性が低いという指摘をしているため、名誉毀損の問題として捉える余地がある」と清水弁護士は述べます。しかし、その他の「感覚が完全にバグってるね」「やっぱり親のエゴが酷いな」といった投稿については、もっぱら名誉感情侵害の問題として扱われることになるとの見解を示しています。つまり、表現の自由は尊重されるべきですが、それが他者の尊厳を著しく傷つけ、社会的に許容される範囲を超える場合には、法的な責任を問われる可能性があるのです。
インターネット上での発言は、その匿名性から軽視されがちですが、その内容が特定の個人に対して誹謗中傷にあたる場合、名誉毀損や名誉感情侵害として法的な問題に発展する可能性が十分にあります。今回の辻希美さん夫妻の件は、名前の是非だけでなく、オンラインでのコミュニケーションにおける倫理と責任を改めて考えるきっかけとなるでしょう。
参照元: