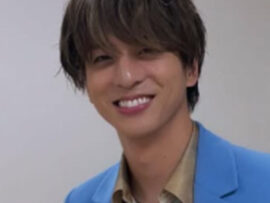高齢者の資産運用と生活資金確保を両立させる画期的な制度として、高齢者向けの少額投資非課税制度(NISA)「プラチナNISA」の創設が検討されています。 本記事では、プラチナNISAの概要、メリット・デメリット、そして今後の展望について詳しく解説します。
プラチナNISAとは?
プラチナNISAとは、65歳以上の高齢者を対象とした新しいNISA制度です。最大の特徴は、従来のNISAでは対象外とされていた「毎月分配型」の投資信託も投資対象に含まれることです。
 alt
alt
従来のNISAは長期的な資産形成を目的としていましたが、プラチナNISAは高齢者の生活資金ニーズにも対応することを目指しています。 金融庁は、2026年度の税制改正要望に盛り込む方向で調整を進めています。
メリットとデメリット
プラチナNISAには、以下のようなメリットとデメリットが考えられます。
メリット
- 毎月分配型投資信託を活用することで、安定的な収入源を確保できる可能性がある。
- 非課税で投資できるため、運用益を最大限に活用できる。
- 生活資金を確保しつつ、資産運用による資産増加も期待できる。
デメリット
- 毎月分配型投資信託は、元本割れのリスクもある。
- 分配金が必ずしも安定しているとは限らない。
- 投資信託の手数料などのコストも考慮する必要がある。
例えば、ファイナンシャルプランナーの山田花子さん(仮名)は、「プラチナNISAは、高齢者の生活を支える上で有効な手段となり得ますが、リスクについても十分に理解した上で利用することが重要です」と指摘しています。
今後の展望
自民党の「資産運用立国議員連盟」は、プラチナNISAの創設に加え、NISAの「つみたて投資枠」の年齢制限引き下げも提言しています。
現在、NISA口座数は増加傾向にあり、多くの人々がNISAを活用して資産運用を行っています。プラチナNISAの導入により、高齢者の資産運用ニーズへの対応がさらに進むことが期待されます。

プラチナNISAは、高齢者の資産運用と生活資金確保の両立を可能にする画期的な制度となる可能性を秘めています。 しかし、投資にはリスクが伴うため、導入前に制度の詳細をよく理解し、自身の資産状況やリスク許容度に合わせて慎重に検討することが大切です。 今後の動向に注目が集まります。