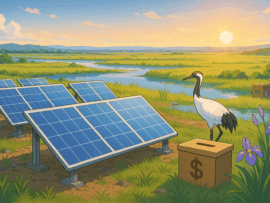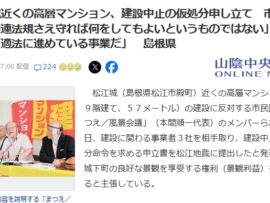ひきこもり、それは社会との繋がりを断ち、家に閉じこもる状態。長期化し、高齢の親が中高年の子を支える「8050問題」、そして「9060問題」へと深刻化しています。この記事では、40年間のひきこもりを経験し、55歳で社会復帰を果たした国近斉さんの物語を通して、ひきこもりの現実、そしてそこから抜け出す希望について探ります。
きっかけは偏差値の高い高校進学、そして苦悩の日々
 山口朝日放送のドキュメンタリー番組に出演した際の国近さん
山口朝日放送のドキュメンタリー番組に出演した際の国近さん
穏やかな笑顔でインタビューに答える国近さん。その姿からは、40年もの長い間、ひきこもりだったとは想像もつきません。山口県在住の国近さんは、高校中退後、約40年間ひきこもり状態でしたが、55歳で社会との接点を取り戻し、今ではハウスクリーニングの仕事に従事し、地域活動にも積極的に参加しています。
国近さんがひきこもるきっかけとなったのは、偏差値の高い高校への進学でした。中学時代の友人からの誘いで受験し、合格したものの、学業についていけず、次第に学校に行かなくなりました。「どうしよう」という不安を抱えながら、家と学校の間を彷徨い、最終的には家に引きこもるようになってしまったのです。
両親は仕事で忙しく、国近さんの異変にすぐに気づくことはありませんでした。しかし、学校からの連絡で事態を知り、「どうして行かないのか」「家で何をしているんだ」と問いただしたといいます。
高校2年生の時、学校からの勧告で中退。その後、友人に誘われて新聞配達を始め、約2年間続けました。しかし、友人が大学進学で県外へ出て行くと、働く気力を失い、新聞配達をやめてしまいます。その後、親戚の勧めで造船所で働きましたが、それも数ヶ月で辞めてしまいました。
 厚生労働省のひきこもり支援セミナーに参加した際の国近さん
厚生労働省のひきこもり支援セミナーに参加した際の国近さん
両親の理解と、静かな40年間
それ以降、国近さんは仕事を探そうという気力もなく、家にこもるようになりました。テレビを見たり、掃除や片付けをしたり、静かな日々を送っていました。「ひきこもり支援の専門家、山田先生」は「家族の理解と受容が、ひきこもりからの回復に大きく影響する」と指摘しています。国近さんの両親は、彼を厳しく責めることはせず、「3人仲良く普通に暮らせたらそれでいい」というスタンスで接していました。この両親の理解と受容が、国近さんを支えていたのかもしれません。
そして、社会復帰へ
国近さんは55歳で、NPO法人「ふらっとコミュニティ」の支援を受け、社会復帰への道を歩み始めました。ハウスクリーニングの仕事を見つけ、地域活動にも参加するようになりました。国近さんの物語は、yab山口朝日放送のドキュメンタリー番組「国近さんの日記 ひきこもり40年 それから…」で紹介され、大きな反響を呼びました。多くのひきこもり当事者や家族から「勇気をもらった」という声が寄せられています。
国近さんの経験は、ひきこもりからの回復に希望を与えてくれます。ひきこもりは、決して出口のない迷路ではありません。適切な支援と、周囲の理解があれば、社会復帰への道が開けることを、国近さんの物語は示しているのです。