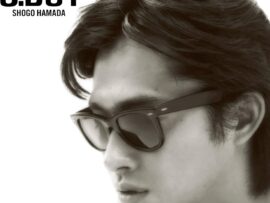日本の食卓に欠かせないコメ。備蓄米の放出後も価格高騰が続いており、私たちの生活に大きな影響を与えています。一体なぜコメは足りないのでしょうか? 過去のコメ政策を振り返りながら、日本の農業の未来について考えてみましょう。
減反政策に翻弄された大潟村:コメ作りの夢と現実
秋田県にある大潟村。かつて琵琶湖に次ぐ広さを誇った湖を干拓して作られた、まさにコメを作るために生まれた村です。国策によって整備された広大な土地で、農家たちは希望に満ち溢れていました。しかし、その夢は長くは続きませんでした。
 大潟村の広大な水田
大潟村の広大な水田
入植からわずか3年後、政府は「コメを作るな」という減反政策を打ち出しました。食生活の多様化によるコメ需要の減少と、余剰米の発生がその背景にありました。コメ農家は大きな打撃を受け、田んぼでウナギや牛を育てたりと、様々な方法で生き残りを図りました。
大潟村も例外ではなく、コメ以外の作物を作るよう要請されました。しかし、干拓地である大潟村の土地は畑作に適しておらず、農家たちは苦境に立たされました。
村は減反政策に従う農家と反対する農家に分裂し、深刻な対立が生じました。涌井徹さん(76)は、減反政策は農家の生産意欲を削ぐものだと反対の声を上げ続けました。
減反政策の光と影:生産調整と所得保障のジレンマ
減反政策は、コメの生産量を調整し価格の安定を図る目的で導入されました。協力した農家には補助金が支給され、所得の維持が図られました。しかし、この政策は日本の農業に大きな変化をもたらしました。
農家の高齢化と後継者不足、耕作放棄地の増加など、様々な問題が浮き彫りになりました。 食料自給率の低下も深刻な問題です。
未来への展望:持続可能な農業を目指して
コメ不足と価格高騰は、私たちに日本の農業の現状を改めて考えさせる機会となっています。 食料安全保障の観点からも、持続可能な農業を実現していくことが重要です。
技術革新、ブランド化、流通改革など、様々な取り組みが求められています。 消費者も、国産農産物を積極的に購入することで、日本の農業を支えることができます。
専門家の意見:農業経済学者 佐藤一郎氏の提言
「減反政策の見直しだけでなく、スマート農業の推進や輸出戦略の強化など、多角的なアプローチが必要だ」と農業経済学者の佐藤一郎氏は指摘します。 生産者、流通業者、消費者が一体となって、日本の農業の未来を創造していく必要があるでしょう。
日本の食卓を守るため、私たち一人ひとりができることを考えてみませんか?