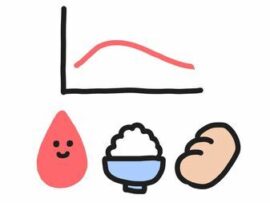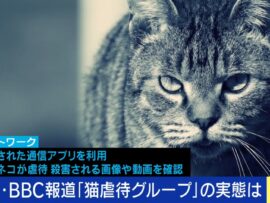「子育て中の女性のスキルアップを後押しするため、必要な施策を検討していく」。石破首相の言葉に反発する女性が多いのはなぜか。ジャーナリストの池田和加さんは「男女の賃金格差の解消や家事・育児・労働の公平な分担を可能にする社会の実現こそが、少子化の改善や企業の持続的成長、日本社会の未来を支える鍵となる」という――。
「子育て中の女性のスキルアップを後押しするため、必要な施策を検討していく」と4月13日に発言した石破首相。女性のために、子育てと仕事を両立しやすい環境を作ることを強調したが、Xでプチ炎上した。首相の発言に対し、「男性育児のほうが先では?」「子育て支援を増やせば?」などの批判が飛び交った。
筆者も、「子育て中のスキルアップ」発言にイラっとした一人である。そう言えば、昨年9月にも、首相が放った「少子化の本質は母親が少なくなる『少母化』であり、結婚したくてもできないほうに光を当て、望む人が結婚できるように、人口減少に必ず歯止めをかける日本をつくっていく」にもモヤモヤを覚えた。いずれの発言も本人はよかれと思って言ったのかもしれないが、逆効果だった。多くの女性が首相の言葉に強烈な違和感を覚えたのはなぜか。
■「少母化」は政府と企業が引き起こした社会構造の結果
まず、「少子化の本質は母親が少なくなる『少母化』」という言葉を見てみよう。
確かに、1970年代から1980年代前半生まれの「団塊ジュニア世代」(第2次ベビーブーム世代)を含む「ロストジェネレーション」が未婚化・晩婚化し、少子化が進んだため、1990年代後半から2000年代に第3次ベビーブームが起きてもよかったが、発生しなかった。石破首相が言ったように、現在、出産可能年齢である20代から30代の女性人口が確実に減少しているのは事実だ。
しかし、出産可能女性の人口減少という現象は、人口動態の結果であり、少子化の根本“原因”ではない。今さら出産可能な女性の数を増やす政策を作ることは100%不可能なのに、なぜ少子化の本質として、母親が少なくなる「少母化」に言及したのか。
ロストジェネレーションは、バブル崩壊後の就職氷河期、アジア通貨危機やリーマンショックに直面した。政府は彼らを救うどころか、派遣労働を解禁して非正規雇用を一気に増加させた。企業と政府による雇用制度や経済政策が大きな要因で未婚化と晩婚化、その延長線上で出生率の低下が進んだのは明らかだ。それにもかかわらず、少子化を「少母化」と、結婚を選ばなかった「女性の選択」が主因であるようににおわせ、少子化の「本質」(石破首相の言葉)である政府や企業の責任から目をそらせようとしていると受け取られてもおかしくない。