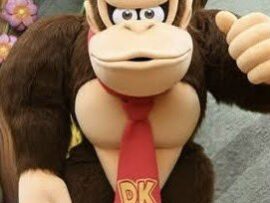同年代だったあの女性のことを今も忘れることはない。東京・多摩地域北部の村山村(現武蔵村山市)にかつてあった東京陸軍少年飛行兵学校。そこで働いていた池谷タカさん(99)は80年前を回想し、「空襲警報が連日鳴っていて、朝に学校へ向かいながら今晩は家で眠れているだろうかと考える毎日だった。そんな時にあの出来事は起こった」と語り始めた。
池谷さんは洋裁学校を卒業後の1943年1月、東京陸軍航空学校(4月に東京陸軍少年飛行兵学校と改称)に就職した。その3年前に母を亡くし、自宅近くにあったことから父に勧められたのがきっかけだった。面接を受けると、「明日から来い」。即採用だった。
その学校は15、16歳ほどの少年に軍人としての基礎教育を行うため、37年に創設された。卒業後は航空機の操縦・整備・通信の上級校へと進み、各部隊に配属された。正門をくぐると60ヘクタールを超える敷地に講堂や学舎などが建ち並んでいた。池谷さんは生徒が訓練で使う剣道用具を修理する部署に入った。そこでは先輩の女性から嫌がらせを受けるつらい日々が待っていた。
弟のような年ごろの生徒たちとの交流はなく、遠くからグライダーの滑空訓練などの様子を眺めるくらいだった。それでも厳しい訓練に明け暮れる生徒たちの心情を垣間見られる機会はあった。上官の男性らが「ゆうべ、おっかさんを思い出して泣き出してしまった生徒がいて困った」などと話すのが耳に入ってきた。
42年に入学したさいたま市の瀬戸山定(さだむ)さん(99)は「訓練は厳しくて、できないことがあると『同じように飯食って寝てるのにどうしてできないんだ』と皆の前で叱られた」と振り返る。操縦士を志したが、「反射神経が良いから向いている」と勧められて通信兵になった。
卒業生の中には特攻隊員となった者も多い。瀬戸山さんは「寮は4人部屋で、固い絆で結ばれた。同期が亡くなったと知った時はその無念を思うと言葉にならなかった」と振り返る。
学校を巣立った若者たちが戦場で犠牲になる一方、学校も米軍の標的とされた。
45年4月中旬。池谷さんも出勤していた平日の午前10時を過ぎた時だった。米軍機のB29とP51が学校を襲来した。その半月前には、爆撃で生徒4人が亡くなっていた。散り散りに逃げ、上空に機体が見えなくなると、皆で互いの名前を呼び合った。学校敷地の雑木林には「たこつぼ」と呼ばれる1人用の防空壕(ごう)があった。
「ハナさーん、ハナさーん」。いくら呼んでも返事はなかった。たこつぼの辺りで機銃掃射に後ろから首付近を撃ち抜かれた女性がいた。食堂炊事班の石井ハナさん。18歳だった。同様にたこつぼに逃げ込んだ人たちはいたが、その日の犠牲者はハナさん1人だった。
池谷さんは張りのある声で言う。「あの時、どうしてハナさんに直撃してしまったのか。私は今こうして話をしているけど、ハナさんの生涯はそこで終わってしまった。生きている者が平気でただ暮らしているだけでいいのかなって思う」
池谷さんは戦後まもなく父も亡くし、51年に結婚した。少年飛行兵学校の敷地が払い下げられると、義父がその一部を購入し、耕作を始めた。池谷さんが農作業に励んでいると、学校跡を訪ねた元生徒たちが思い出話を聞かせてくれた。
その地に居を構え、2003年には元生徒らが集えるようにと、うどん屋「翔(しょう)」(現在は閉店)と私設資料館「少飛思い出館」を開いた。隣接する330平方メートルの土地を市に寄付し、16年に開館した市立歴史民俗資料館分館が少年飛行兵学校の歴史を今に伝えている。
「ハナさんの命日のこの季節になると、子どもたちに当時の話を聞かせてきた。亡くなった場所には毎年お花をお供えしている」。子ども4人に、孫が6人、ひ孫も3人いる池谷さんはそう話す。ハナさんの実家は武蔵村山市の東隣の東大和市にあったと記憶していた。記者が訪ねたが、実家は跡形もなく、近所にもハナさんの記憶が残る人はいなかった。しかし、高台にあった石井家の墓の墓誌にハナさんの名はしっかりと刻まれていた。
4月中旬、池谷さんも訪れたことがなかったその墓を次女の美代子さん(70)が訪ねた。足腰が弱り、墓参がかなわなかった池谷さんに代わって静かに手を合わせた。「母の代理で来ました。ハナさん、安らかにお眠りください」
同じ日、ハナさんが亡くなった雑木林があったとみられる空き地にも美代子さんは花を手向けた。
ハナさんら炊事班の女性たちの穏やかな顔が並ぶ写真を、池谷さんは優しく見つめた。「この地に少年飛行兵たちを送り出した学校があったこと。18歳の女性が亡くなる悲惨な出来事があったこと。命の続く限り伝えていきたいと思う」【関谷俊介】