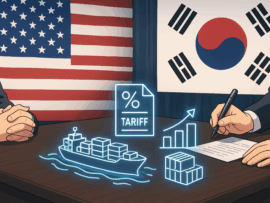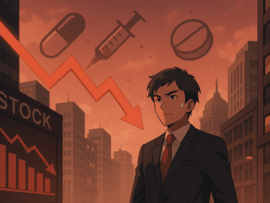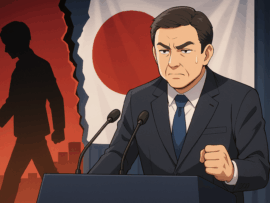[ad_1]
どこの世界でも出世争いは付きものだが、とりわけ官僚の世界は今も昔も競争が激しい。試験の点数で後れを取った者が逆転するには、何かしらの政治力を使うか、あるいはよほどの幸運に恵まれるか、いずれかが必要だという。
その両方を使って、外務次官、さらには総理大臣の地位まで上り詰めたのが、戦後日本を代表する名宰相として知られる吉田茂である。近代史家で、駒澤大学教授の熊本史雄さんの新刊『外務官僚たちの大東亜共栄圏』から、吉田茂の浮き沈みの激しい外務官僚時代を再編集して紹介する。
***
戦後日本を代表する政治家として、吉田茂(1878―1967)の名が挙げられる。1946年5月に第45代総理大臣に任じられ、計5次にわたって政権を担った吉田は、良く知られているとおり、外務省出身者であった。「戦争に負けても外交に勝った歴史はある」との信念のもと、GHQ総司令官のマッカーサーとも堂々と渡り合うなどして戦後日本を再生させた吉田には、岳父に大久保利通の次男・牧野伸顕を持つという血筋の良さも相まって、日本政治の中央を歩み続けてきたイメージがあるかもしれない。
だが、戦後期の活躍から導かれるそうした華やかなイメージとは裏腹に、戦前期の吉田は、外務省内で主流とはいえない存在だった。外交官の花形は在外勤務先として欧米に赴くのが常であった当時の外務省にあって(例えば、幣原喜重郎など)、吉田は、むしろ傍流に位置していた。というのも、1906年7月に東京帝国大学法科大学を卒業し、同年9月の第15回外交官及領事官試験に合格した吉田は、同年11月に外務省に出仕すると、領事官補として最初の任地・天津に赴き、以後、約20年にわたって主に中国畑を歩むことになるからである。ちなみに、同期入省の試験合格首席は、広田弘毅だった。
若き日の吉田は、中国に強硬的な態度で臨む外交官だった。それは、「強硬外交」と形容される田中義一内閣(田中は外相も兼摂)の外交方針を凌ぐほどに際立っていた。たとえば、東方会議(1927年6〜7月開催、在満洲権益の特殊性を確認)開催前に田中が「支那のことは支那人をして自ら之を収めしむべし」と対中国不干渉方針を掲げたことに対し、奉天総領事として会議に参加した吉田は、意見書「満蒙問題ニ関スル件」を亜細亜局長の木村鋭市に宛て、「先ず以て張作霖従来の内外に対する態度の物議あるを遺憾とするの意を示し速に昨の非なるを知りて反省の実を明にする」ことを主張した。「昨の非」とは、第1次・第2次奉直戦争(1922年・24年)、郭松齢事件(25年)と立て続けに内戦に明け暮れ、崩壊しかけている東三省(奉天省、吉林省、黒竜江省)の経済状況を顧みようとしない張作霖の態度を指している。
東方会議終了後には、張作霖の兵工廠への引込線であった京奉線(北京―奉天)の満鉄線横断を阻止しようとするなど、軍部顔負けの強硬ぶりを示したのだった。そのようにして自らの存在を田中にアピールした吉田は、省内の主流派を差し置いて、外務次官の椅子を手に入れることに成功する。むろん、そうした態度は、田中の強硬外交を批判してやまなかった幣原とは相容れなかった。幣原は、「第1次幣原外交」期までの間、吉田を取り立てて重用しようとはしなかった。
ところが、両者のそうした関係に転機が訪れる。田中内閣が総辞職した後、浜口雄幸内閣の外相に就任した幣原は「第2次幣原外交」の始動に際し、外務次官に吉田をそのまま起用したのである。この人事は、吉田にとってまさかのことだった。田中に取り入ってまで次官に就任した自分を、幣原が留任させる筈がないと考えていたのだ。おそらく幣原としては、外交の継続性を重視して、吉田を次官に留任させたのだろう。要は、外交を政局の外に置くことにしたのである。
ここに外交官としての吉田の転機があったとみるべきだろう。戦後の回想録ながら、「日本の外交的進路が、英米に対する親善を中心とする明治以来の大道に沿うものであるべき」と語る吉田は、事実、これを機に英米との距離を縮める立場へと変わっていった。たとえば、1931年3月に在イタリア大使に赴任した際には、第1次世界大戦の敗北から立ち直り、急速に軍事力を強化していたドイツに日本が接近することに常に警戒を示したのである。それゆえ、省内の枢軸派からは「親英米派」とみなされた。さらに1936年には在英国大使として赴任する。だが、ここで吉田は対英協調論者として挫折を味わうことになる。
1934年から36年にかけて、イギリスは大蔵省主導のもと、経済使節団を3度立て続けに訪日させた。とくに、35年・36年と2度にわたって訪日したリース・ロス使節団は、日英協調のプランを携えていた。1度目の訪日時には、
(1)日英共同による中国の幣制改革の実施
(2)中国への借款供与への日本の協力
(3)満洲国に中国の債務を継承・分担させたうえでの中国による満洲国の承認
という案を示し、日本側の意見を訊いてきたのである。これは、〈間接的な満洲国承認プラン〉とでもいうべき妙手で、満洲国建国以降、国際社会から孤立しつつあった日本に差し伸べられた〈救いの手〉でもあった。
だが、イギリスの影響力が満洲国へ波及することを恐れた軍部の反対により、日本はこのプランを断ってしまう。その後、対日外交におけるイギリス大蔵省の影響力は減退し、代わって日本を警戒する外務省が主導することとなった。吉田がイギリスに赴任したのは、まさにそうしたタイミングだった。吉田は日英協調を模索したが、もはやそれを実現できる政治・外交的環境ではなかった。何ら有効な手を打てないままに翌年、日中戦争が勃発し、日英関係は悪化の一途を辿る。失意の吉田は1939年に待命大使となり、外交の一線から退いた。終戦間際の1945年4月には、早期終戦を提言する近衛上奏文に協力したことにより、憲兵隊に拘束され40日あまり投獄される。まさに雌伏の時期を余儀なくされたのだった。
[ad_2]
Source link