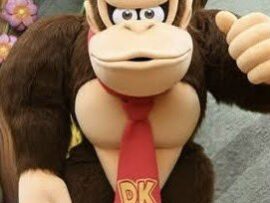兵庫県の斎藤元彦知事に対する内部告発文書をめぐり、斎藤知事が3月に発言した公益通報者保護法の解釈につき、消費者庁が4月にメールで「助言」を行ったことが物議を醸している。
【画像】消費者庁は体制整備義務の対象となる「公益通報者」を「内部通報者」に限っていない
斎藤知事は今年3月、公益通報者保護のための体制整備義務の対象は「内部通報に限定されるという考え方もある」と述べた。これに対し、消費者庁は4月8日にメールを送り「公式見解とは異なる」と指摘した。
また、14日の参議院本会議での公益通報者保護法の改正案審議でも、伊東良孝担当大臣が、上記体制整備義務の対象は「外部への公益通報者も含まれる」と答弁した(社民党・大椿裕子議員の質問に答えて)。
地方自治体の長は、国が示す法解釈に従う法的義務を負うのか。神奈川大学法学部の幸田雅治教授(地方自治法)に聞いた。
幸田教授は元総務省自治行政局行政課長で、弁護士として、適切な公益通報制度のあり方も含めて検討する日弁連の「自治体の内部統制の在り方に関する検討チーム」の委員を務めている。
斎藤知事の法解釈は「十分、成り立ち得る」
まず、そもそも斎藤知事の公益通報者保護法の解釈は成り立ちうるのか。
実際の公益通報者保護法の関連条文を確認しよう。11条2項は、「通報者を保護する体制を整備する義務」について規定している。
【公益通報者保護法11条2項】
「事業者は…3条1号および6条1号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない」
ここでいう「3条1号および6条1号に定める公益通報」とは「役務提供先等に対する公益通報」すなわち「内部通報」をさす。
この条文の解釈について、斎藤知事は、「内部通報」についてのみ、通報者を保護する体制を整備すればよいと解釈している。
他方で、消費者庁の解釈では、監督官庁(2号)や報道機関等(3号)への「外部通報」についての通報者保護の体制整備が「その他の必要な措置」に含まれるということになる。
幸田教授は、「法律の条文を素直に読めば、斎藤知事が示す『内部通報に限定される』という解釈はむしろ自然であり、十分に成り立ち得る」とする。