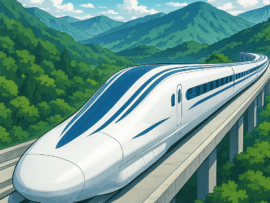広島市立工業高校の元生徒が、在学中に受けた生徒指導は違法だとして広島市に損害賠償を求めた裁判で、広島地裁は5月27日、市に20万円の支払いを命じる判決を下した。報道によると、この生徒は2021年に入学後、授業中にタブレットゲームをしたり、教師に「死ね」と発言したりするなど問題行動を繰り返したため、翌年9月に校長が生徒の母親と面談。その際に校長が「明日から学校に来させないでください」と伝え、これを受けて生徒は転校したという。
判決は、校長の発言を「家庭反省指導」と認定。その上で、発言の趣旨や反省期間などを生徒側に十分に伝えなかったこと、また指導を受け入れるか判断するための必要な情報を提供しなかったことを指摘した。「教育を受ける機会の制限との関係で、必要な配慮を著しく欠いた」として、学校側の対応の違法性を認めた形だ(朝日新聞)。一般的に考えれば、授業妨害や暴言を繰り返す生徒への指導は学校として当然行うべきもの。そのため、この判決は教育現場に衝撃を与え、「なぜ問題行動を繰り返した生徒側が勝訴?」「授業中にゲームや暴言をしておいて、『来るな』と言われたら『高校に行けなくてショック』とはどういうことか?」など、ネット上でも波紋が広がっている(とれんどねっと)。
 授業中にタブレットを操作する手 学生の問題行動を示す一例
授業中にタブレットを操作する手 学生の問題行動を示す一例
争点は「退学処分」ではなく、手続きの瑕疵
当初、この事案は懲戒による退学処分の妥当性が争われた訴訟であると誤解する向きもあった。しかし、複数の報道(広島家族RCCなど)を確認すると、「高校の転学めぐる訴訟」「違法な無期停学処分を認定」といった文言が見られ、争点が異なることがわかる。原告である元生徒側は、退学そのものの是非ではなく、適正な手続きを経ずに転校を余儀なくされたことの違法性を訴えたのである。
そもそも今回の学校側の対応は、正式な懲戒処分としての退学処分ではない。広島市側も「校長の発言は、退学処分に当たらず、自主的な欠席を促す指導として行った」と主張している。そして、判決でも校長の発言は懲戒ではなく「家庭反省指導」という位置づけであったと認定されている。では、なぜ指導が違法とされたのか。ここが本件の核心であり、「懲戒」と「指導」の違い、そして「家庭反省指導」における手続きの必要性が争点となった。
学校が生徒に対して行う措置には、学校教育法に基づく「懲戒」と、それ以外の「指導」がある。懲戒には停学や退学といった重い処分が含まれ、これらを行う際には、生徒や保護者に弁明の機会を与えたり、書面で理由を通知したりするなど、一定の手続きが求められる。これは、生徒の学習権や権利を保障するためである。一方、「指導」はより広範で柔軟なもので、問題行動の改善などを目的に行われる。家庭反省指導もこの指導の一つであり、生徒を一時的に自宅で反省させることを目的とする。
しかし今回の判決は、校長の発言が形式的には懲戒にあたらない「指導」であったとしても、その実質が生徒に学校への登校を事実上不可能にし、教育を受ける機会を制限するものであったと判断した。そして、そのような実質を持つ指導を行うにあたっては、懲戒処分ほど厳格ではないにしても、生徒側が指導の意図、期間、そして学校に戻るための条件などを理解し、その指導を受け入れるかどうかを判断できるような十分な情報提供と、必要な配慮が不可欠であるとした。本件では、校長の発言が突如として行われ、期間も示されず、今後の手続きについての説明も不十分であったため、「必要な配慮を著しく欠いた」として違法とされたのである。
判決の意義と教育現場への影響
今回の広島地裁の判決は、生徒の問題行動に対する学校の「指導」が、たとえ懲戒処分という形式をとらない場合でも、その実質が生徒の学習機会を制限するものであれば、学校は説明責任を果たし、必要な手続き的配慮を行わなければならないことを明確にした。これは、学校が問題行動に対し、懲戒のような正式な手続きを避けつつ、事実上の排除に近い対応を取る場合の限界を示唆するものであり、教育現場における生徒指導の方法や手続きについて、改めてその適正性が問われる契機となるだろう。生徒指導は教育上不可欠だが、その実施においては、生徒の権利、特に教育を受ける権利への配慮が常に求められるという基本原則を再確認させる判決と言える。
参考文献:
- 「学校に来させないで」校長の発言巡り高校側敗訴「必要な配慮欠く」[広島県]:朝日新聞
- 授業中ゲーム暴言生徒の登校禁止通告でなぜ学校敗訴?理由判明(とれんどねっと)
- 校長から「学校に来させないでください」と転校をした元生徒の裁判 「必要な配慮を欠いた違法行為」と広島市に20万円の支払いを命じる広島地裁(広島家族RCC)