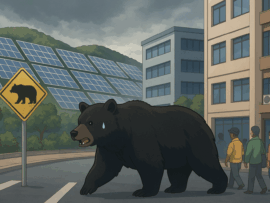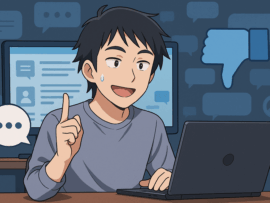「送迎保育ステーション」は、通勤中の保護者から子どもを預かり、定員に空きのある遠方の保育所へのバス送迎を代行する拠点だ。待機児童解消のために約四半世紀前に始まったが、普及が伸び悩んでいるのが現状だ。こども家庭庁によると、2022年度末時点で全国35自治体の導入にとどまり、特に九州での導入は少ない。識者からは「認知度不足が一因」との指摘がある。本記事では、その現場を訪ね、課題と将来性を探る。
神戸市の現場から見たメリット
2024年5月下旬、神戸市のJR舞子駅近くにある送迎拠点「森の駅」を訪ねた。社会福祉法人が運営しており、小規模保育所も併設されている。園児たちは朝、ここで保育士と午前9時ごろまで過ごし、専用バスで約15分の認定こども園へ移動。夕方バスで戻り、保護者を待つ。
 かわいらしい装飾が施された神戸市の送迎保育ステーション外観
かわいらしい装飾が施された神戸市の送迎保育ステーション外観
年長の次男(5)を利用させている公務員の女性(31)は、「ここがないと働く時間を短縮せざるを得ない」と話す。勤務先からJRで舞子駅まで戻る女性にとって、駅隣接の拠点は極めて便利だ。以前は自宅から別の保育所に片道20分歩いて送迎する必要があった。森の駅利用を始めてからは、起床時間を午前5時半から1時間遅らせることができ、送迎時間が短くなったことで早朝や延長の料金も月約5千円節約できたという。
送迎拠点の玄関で迎えに来た保護者と会話する子どもたち
神戸市は2021年度から公募による送迎拠点を鉄道沿線に設け、現在は8カ所で計141人が利用している。2022年度以降(4月1日現在)は待機児童ゼロだが、子育て世帯の支援のため継続。女性は「働く親にとって、時間に余裕ができるのが何より大きい」と笑顔を見せた。
導入の歴史と広がり
送迎保育ステーションは、待機児童解消を目的に2000年代に一部自治体が開始した。国や自治体がバス購入費や運転士、保育士の人件費などを補助している。
2007年度に導入した千葉県流山市は、2005年のつくばエクスプレス開業による人口急増で待機児童が発生。保育施設の増設と並行して拠点を設け、2021、2023、2024年度は待機児童ゼロを達成した。他にも関東や関西の都市部を中心に徐々に広がっている。
九州では、福岡県久留米市が2019年度から年間1500万円の委託料で実施したが、年間最大20人の利用にとどまり、「待機児童ゼロを2年連続で達成した」として2024年度に終了した。一方、神戸市や流山市、堺市、千葉県松戸市など、待機児童ゼロ達成後も継続する自治体は多い。流山市は「やめると保護者によっては送迎が困難になり、再び待機児童が出る恐れがある」と継続理由を説明する。
九州での動きと将来性
導入が少ない九州では、北九州市が2024年9~11月、小倉南区の市立徳力保育所別館を送迎拠点として試行を予定している。モノレールの駅から離れるため「エキチカ」ではないが、「市内や筑豊、京築地域など周辺への車でのアクセスが良い立地で、通勤途中に子どもを預ける需要が見込める」(担当者)ためだという。
北九州市の待機児童は2011年度以降ゼロが続くが、国が保育の受け皿整備が進んだなどとして、2025年度からの保育提供体制に関する計画で、「保育の質」重視への方針転換を表明。同市は利便性を高めるため駐車スペース確保にも取り組む。
社会保障財政が専門の甲南大(神戸市)の足立泰美教授は、「最近は国が補助を拡充しており、今後導入が増える可能性がある」としつつ、「昼間に園児を世話する保育士と保護者が会う機会が少なく、関係が希薄になりがちだ」という課題を指摘する。
運営上の課題と持続可能性
運営側は、全国的に不足している保育士やバス運転士の確保に苦慮している。命を預かる事業であり、バス置き去り防止対策なども含め、安全確保は極めて重要だ。
足立教授は、こうした課題を踏まえ、「持続性のある態勢づくりが求められる」と強調した。
まとめ:普及促進と課題克服へ
送迎保育ステーションは、共働き家庭の通勤負担を軽減し、待機児童解消に貢献する有効な手段となりうる。しかし、その存在はまだ広く知られておらず、全国的な普及は限定的だ。
利用者の利便性向上や、保育士・保護者間のコミュニケーション機会確保といった利用者側の課題に加え、人材確保や安全対策など運営上の課題も依然として存在する。
国の補助拡充などの追い風がある中で、これらの課題を克服し、制度の持続可能性を高めることが、より多くの地域で働く親子の支援につながる鍵となるだろう。