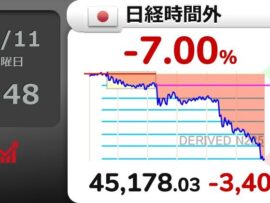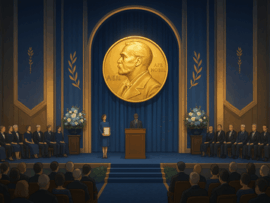中東情勢は新たな段階へと緊迫の度を増している。イスラエルによるイラン攻撃に続き、アメリカがイラン国内の核関連施設を攻撃したことは、地域のみならず国際社会に大きな衝撃を与えている。この複雑かつ危険な状況を、イラン政治・中東国際関係論を専門とする東京外国語大学の松永泰行教授はどう見ているのか。
国際法執行におけるダブルスタンダードの現実
松永教授は、現在の国際秩序が国際法や規範の執行において一貫性を欠いている現実を指摘する。一部の強大な国家が国際法に違反しても事実上不問に付される一方、イランのような国が同じような行為を行ったとされる場合には、強力な制裁が即座に発動されるという不公平な状況が露呈しているという。イランはイスラム法学的思考に基づき、国際法や核兵器不拡散条約(NPT)などの国際的なルールを重視し、義務を遵守する姿勢を堅持していると教授は分析する。これに対し、超大国はしばしばその圧倒的な力を背景に規範を軽視する傾向にあり、イランの姿勢とは対照的だ。
国際規範を無視する西側先進国
今回の事態において、NATO事務総長がアメリカによるイラン攻撃を公然と称賛したり、ドイツのメルツ首相が「イスラエルは我々のためにダーティー・ワーク(汚れ仕事)をしている」と発言したりしたことは、国際法、国連憲章、そして核兵器不拡散条約といった基本的な規範を完全に無視する行為であると松永教授は厳しく批判する。特に、イランの核施設は国際原子力機関(IAEA)の厳重な管理と保護措置の下にあるにもかかわらず、アメリカがこれを攻撃したことは、IAEAの定めるルールそのものへの侵害に他ならない。さらに驚くべきは、G7やNATOといった西側の主要先進国が、この国際法違反を問題視するどころか、むしろ支持している現状だという。
 東京外国語大学教授 松永泰行氏。イラン政治・中東国際関係論が専門。
東京外国語大学教授 松永泰行氏。イラン政治・中東国際関係論が専門。
イランの核平和利用権と不当な侵害
イランは主権国家として、国際法およびNPTによって保障された原子力の平和利用を行う権利を有している。しかし、アメリカの姿勢は次第に一方的になり、イランが持つこの平和利用の権利そのものを否定するに至り、ヨーロッパ諸国もこれに同調している。日本を含む多くの国が当然のように享受している原子力発電所の設置やウラン濃縮の権利を、イランだけが「危険視」され、一方的な爆撃の標的とされることは、NPTが本来目指す趣旨を大きく歪める行為であると教授は指摘する。単なる「疑念」だけを根拠に、一国の正当な権利が侵害されるこのような状況は明確なダブルスタンダードであり、本来であればIAEAによる査察などの平和的な手段によって解決が図られるべき問題である。現在の国際秩序は、1945年の第二次世界大戦の戦勝国が国連安全保障理事会の常任理事国として特権を持つなど、力を持つ者が優遇される構造が制度的に固定されており、その不公正さが今回の事態でも浮き彫りになっている。
周辺アラブ諸国の反応と地域緊張の高まり
イスラエルのガザ地区への大規模な軍事攻撃以降、アブラハム合意を結んだアラブ諸国でさえ、イスラエルに対して批判的な姿勢を示すようになっていた。この流れの中で、イスラエルによるイランへの空爆に対しても、一時的にイランへの同情的な見方が広がった。しかし、アメリカが参入しイランを爆撃した後、イランがカタールにある米軍基地への報復攻撃を行ったことで、状況は変化した。イランは物理的な被害を最小限に抑えるため、カタール側へ事前に通告を行ったとされるが、結果としてカタールの主権を侵害した形となり、一部のアラブ諸国におけるイランへの同情論は後退した。同時に、この報復行動は、イランがペルシャ湾岸に点在する米軍基地や、サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)などを攻撃目標としうる能力を持っていることを明確に示し、これまで潜在的な脅威とされてきたイランの影響力が現実の危険として認識されるようになり、周辺国にさらなる緊張をもたらしている。しかし、松永教授は最後に、忘れてはならない最も重要な事実は、こうした一連の事態のきっかけとなった挑発なき先制攻撃を行ったのは、紛れもなくイスラエルとアメリカであったということだと強調している。

結論
松永泰行教授の分析は、イラン核施設への攻撃を巡る現状が、国際法や規範の軽視、強者によるダブルスタンダードの横行という、国際秩序の根本的な問題を浮き彫りにしていることを示唆している。イランの核平和利用権を認めず、一方的な攻撃を行うアメリカとその同盟国の姿勢は、NPTの理念を損ない、地域の緊張を一層高める結果を招いている。周辺アラブ諸国の複雑な反応も、地域の不安定化を示している。教授は、最初の挑発行為がイスラエルとアメリカからなされた事実を強調し、国際規範の遵守こそが事態打開の鍵であることを示唆している。
参考文献
- AERA 2025年7月7日号
- Yahoo!ニュース(朝日新聞)掲載記事