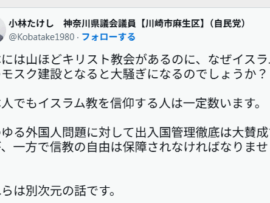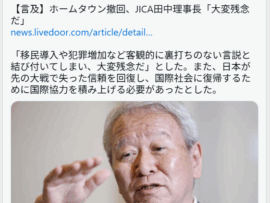日本オリンピック委員会(JOC)は6月26日、新会長に橋本聖子参議院議員(自民党)を選出した。橋本氏といえば、過去にソチ冬季五輪閉会式後のパーティーでフィギュアスケートの高橋大輔氏へのキスセクハラ騒動が報じられたこと、また政治資金収支報告書へのパーティー券収入2057万円の不記載問題(いわゆる裏金問題)で自民党から処分されたことなど、不祥事が相次いでいる人物として知られる。そのため、今回のJOC会長選出報道直後から、SNSを中心に「昭和だったら許されるかもしれないが」「東京五輪のあのすったもんだはどうなったの?」「JOCなんて解体して」といった非難や疑問の声が殺到し、大きな波紋を呼んでいる。
 政治資金の不記載問題を巡り、参院政治倫理審査会に出席後、記者団の取材に応じる橋本聖子氏(2024年3月撮影)
政治資金の不記載問題を巡り、参院政治倫理審査会に出席後、記者団の取材に応じる橋本聖子氏(2024年3月撮影)
さらに、現職の国会議員が公益財団法人であるJOCの会長に就任することについては、政治的な中立性の観点からも問題が指摘されている、と全国紙の記者は述べている。
「再び五輪を招致するのは使命」発言と東京五輪の負の遺産
新たな火種となったのは、橋本新会長が就任会見で「日本が再び五輪を招致していくのは使命だと思っている」と述べたことだ。この発言は、国民の間で根強い東京五輪への不信感と相まって、さらなる物議を醸している。
前出の全国紙記者が指摘するように、東京五輪を巡っては、不正な受注調整による独占禁止法違反で公正取引委員会が7社に約30億円の課徴金納付を命じ、刑事事件でも4社に一審有罪判決が出た談合事件、そして複数の汚職事件が発覚している。こうした一連のダーティーなイメージに加え、多額の税金が投入された経緯から、国民の間には今後のオリンピック招致に対し強い拒否感が蔓延している。
そのため、橋本氏の「五輪再招致」宣言に対しても、「そんな使命いらない」「やるなら私財でやって」「東京五輪のケジメもないまままた五輪とか」といったネガティブなコメントが相次いでいる。掲示板『2ちゃんねる』創設者のひろゆき氏も、自身のX(旧ツイッター)で「税金を使う政治家達は、喜んでイベントを増やす。税金を払う労働者達はイベントを見る暇もなく働き納税する」と投稿し、税金とイベント開催の構造を批判している。
橋本氏が具体的に夏季か冬季か、場所を明言したわけではないが、2021年に夏季の東京大会を開催したばかりであることを踏まえると、次に日本が招致を目指すとしたら冬季大会が現実的だと見られている。
札幌市の空振り招致活動に費やされた27億円
しかし、直近で冬季五輪招致に向けて精力的に活動してきたのは札幌市だったが、2023年に招致活動を停止している。
スポーツジャーナリストによると、少なくとも2022年まではIOC(国際オリンピック委員会)内部で札幌は2030年大会の「大本命」と目されていた。しかし、東京大会の談合事件などが影響し、JOCの山下泰裕前会長がIOCに対し「2030年の招致は難しい」と伝えたところ、バッハ会長が激怒したという経緯があったとされる。その結果、2023年10月のIOC総会で突然、2030年と2034年大会の同時内定方針が発表され、さらに2038年大会の「優先的対話」の相手にスイスが指名されたことで、札幌が少なくとも2038年までは絶望的な状況となり、招致活動停止に至ったと読売新聞が報じている。
札幌市が冬季オリンピック・パラリンピックの招致活動のために費やした費用は、約27億円と発表されている。市の幹部は、招致活動によって「街づくりの加速」や「バリアフリー化」といった成果もあったと説明しているというが、市民からすれば、この巨額な税金が「ムダに消えた」という思いが強いだろう。
札幌市の公式サイトには、招致活動停止について、以下のような声明が掲載されている。
「札幌市は大会招致に向けて動くための足掛かりを失いました。また、気候変動の影響により、冬季大会の在り方そのものの大きな変化が予想されること、そして少なくとも15年先の札幌市がどのような課題を抱え、その解決に向けたまちづくりに対し、大会の開催がどのような効果を発揮するのか見通せないことから、今回の判断に至ったところです」
気候変動によって冬季大会のあり方がどうなるか不透明であることや、十数年先の札幌市の状況が見通せないことなど、招致活動停止の理由として極めて妥当な内容が挙げられている。そして何より、再び数十年先のために、ムダになるかもしれない数十億単位の血税を投じて招致活動を行うべきなのか? 橋本新会長は、こうした過去の経緯や市民感情に対し、今後どのように説明責任を果たしていくのだろうか。