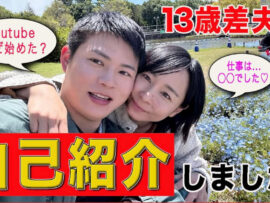GHQ占領下の日本で発生した「下山事件」は、戦後史における最も有名な未解決事件の一つとして現在も多くの謎を残しています。昭和24年(1949年)7月、国鉄(現在のJR)の初代総裁であった下山貞則氏が突然失踪し、翌日、常磐線の線路上で轢死体となって発見されるという衝撃的な展開は、当時から自殺か他殺かを巡る激しい論争を巻き起こしました。この未解決事件は、その複雑な背景と核心に迫る難しさから、長年にわたり人々の関心を引きつけ続けています。
下山事件の概要と当時の社会背景
国鉄初代総裁に就任した下山貞則氏には、占領下の国鉄を立て直すという膨大かつ困難な任務が課せられていました。中でも喫緊の課題は、GHQの民間運輸局(CTS)の意向を受けた約10万人規模の人員削減への対応でした。下山氏は、この人員整理を巡る労働組合との交渉において矢面に立たされていました。彼が東京・日本橋の百貨店から消息を絶ったのは、約3万700人に対する解雇通告が行われた翌日、1949年7月5日の出来事でした。このタイミングは、事件の背景としてしばしば重要視されています。
轢死体発見と真相を巡る大論争
下山氏の轢死体が常磐線綾瀬駅近くの線路で発見されたのは、失踪翌日の7月6日未明のことです。この発見は、即座にマスコミや世論を二分する大論争を巻き起こしました。「自殺説」と「他殺説」(他殺説には左翼テロ説や米軍謀略説などが含まれる)が激しく対立し、複雑な捜査と相まって真相解明は極めて困難を極めました。現在に至るまで公式な解決には至っておらず、多くの書籍や検証番組(近年ではNHKスペシャル「未解決事件」など)が制作され、新たな証言や分析が今も続けられています。この事件は、占領期日本の政治的・社会的な混乱を象徴する出来事として語り継がれています。
 昭和24年(1949年)夏、常磐線綾瀬駅付近での下山事件遺体発見現場。捜査の様子。
昭和24年(1949年)夏、常磐線綾瀬駅付近での下山事件遺体発見現場。捜査の様子。
元警視総監 田中栄一氏の証言
この下山事件において、警視庁の捜査を指揮した当時の警察総監、田中栄一氏(1980年没)は、後に興味深い発言を残しています。田中氏は下山総裁とは東京大学の同期であり、事件の背景を深く知る立場にありました。週刊新潮が昭和46年(1971年)に掲載した記事(「週刊新潮」1971年1月9日号「下山事件 田中・元総監の『死ぬまでいえない』内容」を再編集)の中で、田中氏は事件前々日に見た下山氏の「ただならぬ挙動」について言及しつつも、真相については多くを語りませんでした。彼は度々真相についての判断を求められながらも、このように言葉を濁していました。
捜査の裏にあった影:警視庁とGHQの関係
田中栄一氏が下山事件の真相について「私のイキを引き取る時までいえない」と語った背景には、当時の捜査を取り巻く特殊な状況がありました。占領下の日本において、警視庁の捜査はGHQ、特にウィロビー少将が率いる参謀第二部(GII、諜報・治安担当)やその関連部隊との関係性を無視できませんでした。警察組織がGHQの強い影響下にあったことから、捜査の方向性や情報の扱いにおいて、外部からの圧力や介入があった可能性が指摘されています。田中氏のこの発言は、単なる沈黙ではなく、当時の捜査がいかに複雑で、公にできない要因を孕んでいたかを示唆しているのかもしれません。
下山事件は、初代国鉄総裁の不審死という表面的な出来事だけでなく、その背後にある占領下日本の権力構造、労働問題を巡る対立、そして未解明な部分に隠された「何か」を感じさせる点で、今なお我々の関心を惹きつけ続けています。田中元警視総監の言葉は、事件の闇の深さを改めて浮き彫りにしています。