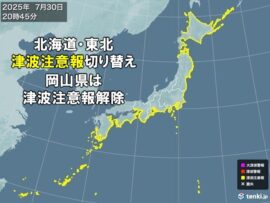日本の農業政策が転換期を迎えています。特に、農地の集約化と大規模化を推進し、生産性の向上を図る動きが活発化しています。農林水産大臣を務める小泉進次郎氏と経済界の代表である経団連が会談し、企業の農業参入を促すために農地の集約化を検討することで合意に至りました。また、農林族の重鎮とされる森山裕自民党幹事長も、農業の生産性向上のため、農地の大規模化を推し進めるための緊急決議を提出するなど、与党内でもこの方向性が強く打ち出されています。しかし、農地の大規模化は本当に日本の農業を救うことができるのでしょうか。東京都議選での自民党の苦戦や来る参院選を控え、党内に焦りが広がる中で、「ほんとうのコメ対策」について、近畿大学農学部の増田忠義准教授(農業資源経済学)がその見解を語ります。
歴史的背景:2009年「石破レポート」と農業政策の変遷
農地の大規模化は、生産コストを大幅に削減できると期待されています。この考え方は新しいものではなく、かつて石破茂氏が農林水産大臣だった時代の2009年にまとめられた「石破レポート」でも示唆されていました。同レポートでは、農水省による生産調整について、様々なシナリオに基づき米価や生産量などを予測しており、生産調整を「緩和」していくことが、米価を下落させつつ大規模農家への農地集約を進めるための最適な選択肢であるとしていました。それから16年の時を経て、「令和のコメ騒動」と呼ばれる状況をきっかけに、日本の農政はかつてないほど注目を集めることとなりました。
政府・与党の最新動向:小泉農水相、森山幹事長、石破首相の提言
こうした状況の中、政府・与党は農業構造改革に向けた具体的な動きを加速させています。6月2日には、森山裕幹事長が農地の大区画化などの整備を実施していくための長期的な対策を小泉農水相に提出しました。さらに同月17日には、小泉農水相が経団連との会談を行い、企業の農業分野への参入を促す目的で、農地の集約を図っていく方針で合意しました。現職の石破茂首相も、農家の所得補償のあり方について、来年6月までには結論を得たいとしており、主要な政治家が農業改革、特に大規模化に焦点を当てています。
 日本の農政改革に取り組む小泉進次郎農水相
日本の農政改革に取り組む小泉進次郎農水相
専門家が指摘する「大規模化」の課題とデータが示す実態
石破首相が農水相時代に掲げた「農家の大規模化を促進し、生産コストを下げる」という政策方針は、現在の議論でも中心となっています。しかし、増田准教授は、今後大規模農家を重点的に支援し、所得補償を一律化していく方向性が取られるのであれば、「やや乱暴な政策の方針」という印象を受けると指摘しています。その背景には、日本の農業が抱える構造的な課題があります。
農水省が公表している令和5年産の米の作付規模別60キログラム当たり生産費のデータを見ると、規模による生産コストの差は歴然です。0.5ヘクタール(ha)未満の経営体では2万7544円、0.5〜1.0haでは2万1821円と高い生産コストがかかるのに対し、30〜50haの経営体では1万1029円、50ha以上では1万220円と、大規模になるほどコストが大幅に低下することが分かります。このデータによれば、0.5ha未満と0.5〜1.0haを合わせた経営体数は35.8万に上ります。これを単純に計算すると、日本の水稲作付面積約145万haのうち、約32%にあたる46万haを、作付面積3.0ha未満の小規模経営体が担っていることになります。つまり、コスト高に悩む多くの小規模農家が、日本の農業生産の相当部分を支えている現実があるのです。専門家の指摘は、大規模化の推進だけでは、この広範な小規模経営体の問題や、地域の実情に即さない可能性があることへの警鐘と言えるでしょう。
結論:大規模化は万能薬か?今後の農政の行方
日本の農業政策は、農地集約と大規模化を中心に据え、生産コストの低減と企業の参入促進を図る方向へ大きく舵を切ろうとしています。これは、石破レポート以来の長期的な課題認識に基づく動きであり、主要政治家のリーダーシップによって推進されています。しかし、データが示すように大規模化が生産コスト抑制に効果がある一方で、専門家は、多くの小規模農家が国土の広い面積を担っている現状を踏まえ、政策の「乱暴さ」に懸念を示しています。大規模化一辺倒の政策が、多様な日本の農業構造や地域社会にどのような影響を与えるのか、そして「ほんとうのコメ対策」とは何なのか。今後の農政の展開と、それが日本の食料供給と農村に与える影響が注視されます。
参考文献
- コメ大臣は本領発揮できるか – Yahoo!ニュース / デイリー新潮 記事
- 農林水産省 令和5年産 米の生産費データ (記事中で言及)