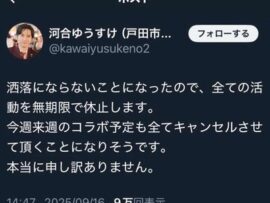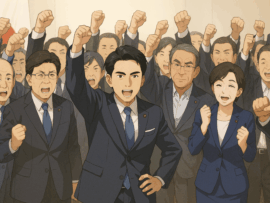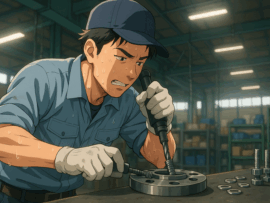なぜ、皇位継承問題は重要なのか。皇室史に詳しい宗教学者の島田裕巳さんは「万が一『天皇不在』という事態になると、日本の国はフリーズし、機能不全に陥ってしまう」と指摘する。天皇、皇后両陛下の長女愛子さまと秋篠宮家の次女佳子さまが日本芸術院賞の受賞者らと懇談されるなど、皇族方の活動が報じられる中で、皇室への関心は依然として高い。しかし、皇統の安定的な継承や皇族数の確保といった喫緊の課題については、国民の十分な理解が得られているとは言い難い状況がある。この問題が単なる伝統や歴史の話ではなく、国の根幹に関わる重要な課題であることを理解する必要がある。
 日本芸術院賞受賞者との懇談に臨まれる愛子さまと佳子さま
日本芸術院賞受賞者との懇談に臨まれる愛子さまと佳子さま
世論はどう見ているか:高まる関心と女性天皇への支持
毎日新聞が今年5月に行った世論調査では、皇室への関心について「大いに」と「ある程度」を合わせて66%が「関心がある」と回答した。これは「関心がない」と答えた33%の倍にあたり、国民の3分の2近くが皇室に関心を寄せていることがわかる。一方で、18歳から29歳までの若年層では「関心がある」が50%に低下しており、「関心がない」が49%とほぼ拮抗している。このことから、若年層における皇室への関心の薄さがうかがえる。
女性天皇については、全体の7割がこれを支持すると回答した。かつて9割を超える支持があった時期もあるが、悠仁親王の誕生により数字は変動した。注目すべきは、今回の調査で女性天皇を否定したのはわずか6%だった点である。女性天皇を容認する声が圧倒的多数を占めている。こうした世論調査の結果は、開会中の国会で議論が進められていた皇統の安定的な継承や皇族数の確保に関する議論と無関係ではない。これらの課題は先送りされたとはいえ、依然として重要な政治課題である。
「天皇不在」がもたらす国の機能不全
では、なぜ皇統の安定的な継承がそれほどまでに問題となるのだろうか。最も端的な理由は、「天皇不在」という事態が起これば、日本の国が停止し、機能不全に陥ってしまうからである。この深刻な事態を国民のどれだけが正確に理解しているかは不明である。
島田裕巳氏の著書『日本人にとって皇室とは何か』でも詳しく説明されているように、日本国憲法は天皇を「国事に関する行為」を行う者と定めている。もちろん、天皇がこれらの行為を独断で行うわけではなく、内閣の助言と承認が必要とされる。しかし、これらの行為は国家運営の根幹に関わる極めて重要なものばかりである。
天皇の「国事に関する行為」とは
日本国憲法によって天皇に定められた国事に関する行為は以下の通りである。
- 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
- 国会を召集すること。
- 衆議院を解散すること。
- 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
- 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
- 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
- 栄典を授与すること。
- 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
- 外国の大使及び公使を接受すること。
- 儀式を行うこと。
これらのリストを見れば明らかだが、いずれも国家運営にとって欠かせない、極めて重大な行為ばかりである。例えば、もし今この瞬間に天皇が不在となった場合、憲法改正や法律の公布ができなくなるだけでなく、国会の召集や衆議院の解散、総選挙の公示といった民主主義の根幹をなす手続きも不可能になる。内閣総理大臣や最高裁判所長官の任命も行えず、外交文書の認証や外国大使の接受も滞る。文字通り、国の最高機関や政府の活動が停止し、国家としての機能が麻痺してしまうのである。
結論:皇位継承問題は国家の存続に関わる喫緊の課題
皇位継承問題は、単に皇室の伝統やあり方を巡る議論にとどまらない。それは日本国憲法が定める天皇の役割、すなわち国家の根幹に関わる「国事に関する行為」の継続性と直結する、国家の存続に関わる極めて重要な課題である。万が一にも「天皇不在」という事態が発生すれば、憲法に定められた国の機能が停止し、未曽有の混乱を招くことは避けられない。世論の動向や若年層の関心の薄さといった課題はあるものの、皇統の安定的な継承と皇族数の確保は、日本の国が将来にわたって機能し続けるために不可欠な喫緊の課題であり、国民全体でその重要性を認識し、議論を深めていく必要がある。
参考文献
- 島田裕巳『日本人にとって皇室とは何か』(講談社現代新書)
- 毎日新聞世論調査(2024年5月実施)
- 日本国憲法
- オリジナル記事: Yahoo News Japan (Source link: https://news.yahoo.co.jp/articles/b05a83c02f1e92c8533f66c1f32929af8ee1d0db)