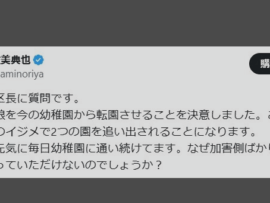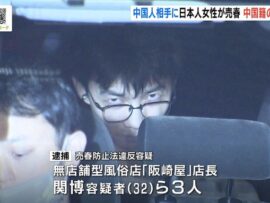現在、日本の高齢者層では「働けるうちはいつまでも」という就業意欲が高まっています。その背景には、生きがいに加え経済的な理由も大きく影響しています。総務省統計局の家計調査では、65歳以上無職夫婦世帯の家計は毎月3万4058円の赤字です。本記事では、内閣府が公表した「令和7年版高齢社会白書」のデータをもとに、シニアの就業意欲、就業率の推移、そして経済的実態を探ります。
高まるシニア世代の就業意欲:「いつまでも働きたい」が最多
収入のある仕事に従事する60歳以上の高齢者への内閣府調査では、彼らの高い就業意欲が示されました。「働けるうちはできるだけ長く働きたい」と回答した人は全体の33.5%で最多でした。他の意向としては、65歳くらいまでが12.9%、70歳くらいまでが22.8%、75歳くらいまでが20.1%、80歳くらいまでが7.4%となっています。この結果から、多くのシニアが従来の定年年齢にとらわれず、長く働き続けることを強く望んでいることがわかります。「仕事をしたいとは思わない」はわずか1.5%でした。
 働く高齢者のイメージ写真
働く高齢者のイメージ写真
高齢者就業率は上昇傾向、制度変更も後押し
実際の高齢者就業率も年々上昇しています。2024年時点では、65~69歳の就業率が53.6%、70~74歳が35.1%、75歳以上が12.0%です。これらの数値は、過去10年間で一貫して上昇トレンドを示しています。
この背景には、法制度の変化があります。2025年4月からは、企業に希望者全員の65歳までの雇用確保が義務付けられ、さらに70歳までの就業機会確保が努力義務となりました。こうした環境整備と、前述のような高齢者の高い就業意欲が相まって、シニアの就業率は今後も高まる見込みです。年金だけでは生活費が不足しがちな経済状況も、「働けるうちは働きたい」という意欲を後押しする大きな要因と言えるでしょう。
まとめ:意欲と現実から見る日本の高齢者就業
内閣府の「高齢社会白書」および家計調査からは、日本のシニア世代が高い就業意欲を持ち、実際に働く人の割合も増加している現状が明確になりました。この背景には、社会とのつながりや健康維持に加え、特に無職世帯における家計の赤字という経済的な現実が強く影響しています。法制度の整備も進み、高齢者の就業は今後さらに加速すると予想されます。しかし、その働き方や経済的安定は、個々人の年金受給額や生活費によって異なります。高齢者が安心して働き続けられる社会の実現に向けた制度やサポートの重要性が改めて浮き彫りになっています。
参照元:
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」(2025年6月10日)
- 総務省統計局 家計調査報告